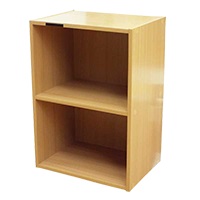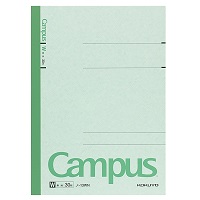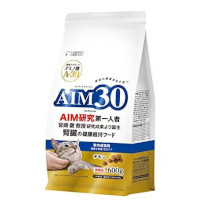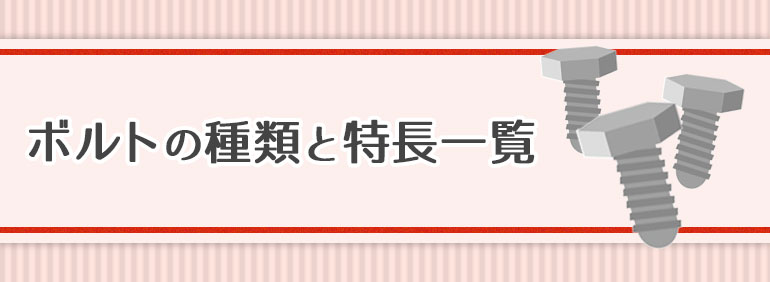目次
1章:ボルトとねじの違い
2章:ボルトの種類と特長
3章:ボルトの規格とサイズの見方
4章:主なボルトの素材と強度
1章:ボルトとねじの違い
ねじは、らせん状の溝のある物の総称です。外側にらせん状の溝が入ったものを「雄ねじ(お ねじ)」、内側にらせん状の溝が入ったものを「雌ねじ(めねじ)」と分類しています。ボルトや コーススレッド、小ねじは雄ねじ、ナットは雌ねじです。
「ねじ」というグループの中に、ボルトやコーススレッド、ナットなどの種類があると考えるとわかりやすいでしょう。
「ねじ」とは、締めつけて物を固定するための部品です。手工具のドライバーや、電動ドライバーなどで締めつけるのが一般的です。
雄ねじと雌ねじで挟み込んで締めるタイプと、ねじ自身が素材に食い込んで溝を作りながら締めるタイプがあります。
ボルトは、ナットなどの雌ねじとともに対象物を挟みながら、回して締めるタイプのねじです。大きいものをボルト、小さいものを小ねじと呼びます。小さな機械から大きな建造物まで、さまざまなところで使われています。
2章:ボルトの種類と特長
ボルトには、頭の形や使用目的などによって、さまざまな種類があり、それぞれに特長があります。DIY で使用されるボルトの種類を一覧にまとめました。
六角ボルト

頭の部分が正六角柱になったボルト、一般的に「ボルト」というと、この種類のものを指す場合が多いです。六角形の部分の二辺をスパナやレンチで挟み込み、締めつけたり緩めたりして使います。
ワッシャーとスプリングワッシャーが取れないように組み込んであるものを座金組込六角ボ ルトといいます。
六角穴付ボルト

円筒形の頭部に六角形の穴があるボルトです。締めつけには六角穴のサイズに合わせた六角棒レンチを使用します。レンチやスパナを使わずに締めつけができるので、機械や電気製品の内部など、狭い場所での締めつけに多用されます。高い締めつけ力があります。
ボタンキャップボルト
頭部が半球形になった六角穴付ボルト。頭部が低くできているため、目立たせたくないところに使われます。
皿頭ボルト
頭部が皿のように平らになった六角穴付ボルト。表面に頭の出っ張りを出したくないところに使われます。皿キャップボルトともいいます。
蝶ボルト

ウイングボルトとも呼ばれます。頭部に蝶のような形をした取手がついており、工具を使わずに手で締めつけや取り外しができるボルトです。取り外す機会の多いところに使われます。
アイボルト
頭部がリングになっているボルトです。穴にワイヤーを通して使います。輸送や機械類の吊り上げに使われます。
U ボルト

両端に雄ねじが切られ、U 字型になっているボルトです。 主に配管(パイプ)を固定するとき に使用します。
アンカーボルト
建造物や設備機器をコンクリートの土台と結合するために、あらかじめ土台に埋め込んでおくボルトです。一度埋め込むと外れないような形状になっています。
通常のアンカーボルトと異なり、コンクリートにハンマードリルなどで下穴をあけて打ち込むタイプのアンカーを、打ち込みアンカーといいます。アンカーを穴に差し込み、ハンマーで叩くことでアンカーの下部が広がるため、土台に食い込んで固定されます。
羽子板ボルト
長いボルトに穴のあいたプレートがついたボルトです。主に木造軸組工法建築物で、梁の両端部に取りつける補強金具として使われます。
スタッドボルト
頭部がない軸部分だけのボルトです。軸の両端か全部が雄ねじになっています。すん切りボルトとも呼ばれます。使用するときまで、ねじの長さがわからないような場合に使います。
ハイテンションボルト

高力ボルトとも呼ばれます。高い強度と強い締めつけ力が特長です。ハイテンションボルトは ボルト・ナット・座金の 3 つで使用します。
ケミカルアンカーボルト

コンクリートにあけた穴に差し込んで、全ねじなどをねじ込むと、カプセル内の接着剤と化学反応して固まるアンカーボルトです。
3章:ボルトの規格とサイズの見方
ボルトに限らず、ねじはミリでサイズを表します。
ボルトのサイズは、パッケージに「M5×12」などと表示がしてあります。この「M5」を「呼び (呼び径)」といい、ボルトの太さを表し、「×12」はボルトの長さを表します。ボルトの長さは、頭を抜いた、ねじが切ってある部分の長さです。この場合は、径 5 ミリで長さ 12 ミリのボルト ということになります。
日本では、ISO 規格(国際標準化機構)と JIS 規格(日本工業規格)が使われていますが、両者の違いをなくしていこうという流れになっています。そのため ISO と JIS は、現在はほぼ同じ と考えても良いでしょう。
ただし、ISO にはない寸法のねじも現場では多数使われているため、JIS 規格として現在も残っているものもあります。JIS 規格が、日本で流通しているねじの規格と考えて良いでしょう。
JIS 規格には、メートルとユニファイの 2 つの規格があります。ユニファイで表す寸法はインチです。規格外の特殊なねじも多様にあります。
4章:主なボルトの素材と強度
ボルトにはさまざまな種類があります。材質、表面処理の方法によって、強度や耐食性などにも違いがあります。目的や用途に合ったボルトを適切に選ぶことが必要です。
素材
- ◆S45C・H・・・機械用炭素鋼 S45 に焼入れ、焼き戻し処理をして強度を高めたもの。
- ◆ステンレス・・・耐食性に優れる。
- ◆アルミ・・・軽量で加工しやすいが、強度に乏しい。
- ◆チタン・・・軽くて強度が高い。耐食性に優れる。
- ◆燐青銅・・・有害物質を含まない合金。強度が高い。
- ◆ポリフェニレンスルファイド(PPS)・・・耐熱性・耐薬品性、寸法安定性に優れる。
- ◆塩ビ(PVC)・・・絶縁性、難燃性、耐候性に優れている。
- ◆ポリプロピレン(PP)・・・軽量で、耐薬品性に優れている。
- ◆ポリカーボネート(PC)・・・無色透明。衝撃に強い。耐熱性に優れ低温にも強い。
表面処理
- ◆ クロメート・・・・・亜鉛メッキ加工処理後の耐食性の低さを補うための加工。六価クロムを主とす る溶液で、表面に酸化被膜を作ったもの。光沢クロメート(ユニクロメート)、有色クロメート、 黒色クロメート(黒亜鉛メッキ)などがある。ユニクロメート(光沢クロメート)は代表的な鉄 の防錆加工で、均一にメッキ加工することができ、低価格なので量産加工に向いている。耐食性 は、黒>有色>光沢となる。
- ◆ 三価クロメート・・・有害物質に指定される六価クロムを使用せず、三価クロムを代用して加工 されたもの。有色クロメートと同等の耐食性を持つ。
- ◆ ニッケル・・・・・・ステンレスや鋳物などの材質に適したメッキ加工。耐薬品性、耐食性に優れてい る。光沢を持ち変色しにくいため、装飾用に広く使われる。
- ◆ クローム・・・・・・下地にニッケルメッキ、その上にクロムメッキを施したもの。耐食性に大変優れ、 高度の光沢を持つ。
- ◆ 黒クローム・・・・・他の黒メッキと比べ、耐摩耗性、耐食性、耐熱性に優れている。漆黒のような 黒色で、装飾性が極めて高い。
- ◆ 黒ニッケル・・・・・ガンメタリックとも呼ばれる。加工時に有害性のある六価クロムを使用する黒クロームの代替品として使われるが、真っ黒ではない。下地にニッケルメッキ、その上に黒色の 亜鉛、ニッケルの合金メッキを貼り、クリアで仕上げ変色を防ぐ。耐食性はニッケルメッキと同等。
- ◆ 黒色酸化被膜・・・・鋼鉄の表面に酸化被膜を形成させ防錆性を持たせたもの。光沢のある黒色。
強度
ボルトは同サイズであっても、材質や熱処理方法によって強度が大きく異なります。ボルトの頭やパッケージに表示されている「4.8」などの数字は、強度区分を表しています。左の数字は引 張強さを表し、この場合は4なので 400N/mm2 となり、400N/mm2 まで壊れません、ということを示しています。右の数字の 8 は、先ほどの引張強さの 8 割が降伏点であるということを示しています。この場合、降伏点は 400N/mm2 の 8 割で、320N/mm2 ということになります。ボルトは、荷重をかけていくと荷重に応じて伸び、荷重を外すと元に戻りますが、ある点を越えると戻らなくなります。この点を降伏点といいます。降伏点を越えて荷重をかけ続けると、ボルトは最終的 に破損します。「4.8」と表示されているボルトは、320N/mm2 以上の引張荷重では使用できないということになります。
JIS では、3.6、4.6、4.8、5.6、5.8、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9 の 10 段階に強度区分が設けられています。ただし、ステンレスボルトは別の規格で表示されます。
ステンレス、チタン、アルミ、ポリプロピレンなど
- ◆ ステンレス・・・・・主に耐食性を目的として使用される。ただし、主成分は鉄なので、使用条件下では錆びることがある。
- ◆ チタン・・・・・・・軽量、非磁性、耐食性という特長を生かし、精密機器の組みつけ部品等にも使われる。
- ◆ アルミ・・・・・・・アルミは軽量で腐食に強いという特長がある。軽量化を目的としたホビー系に使用されることが多い。
- ◆ ポリプロピレン・・・汎用プラスチックの中で最も軽量で、耐薬品性に優れた素材。
その他にも、インコネル、チタンパラジウム、セラミックなど特殊素材のねじがあります。