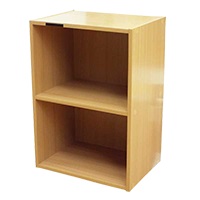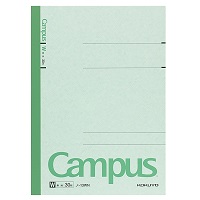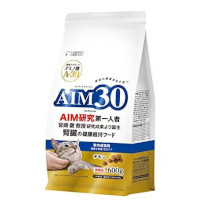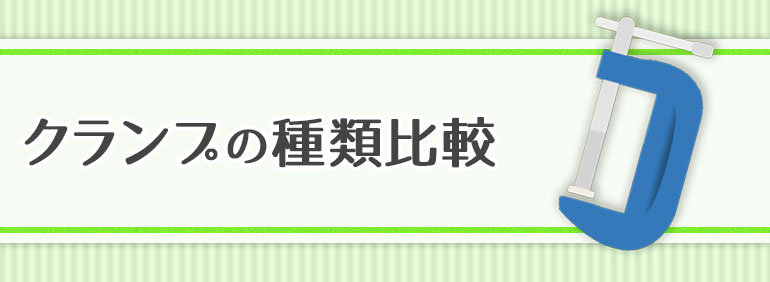目次
1章:クランプとは?
2章:クランプの種類
3章:クランプの許容加重
4章:用途別クランプの選び方
5章:クランプの使い方
6章:使い方の注意点
まとめ
1章:クランプとは
クランプ(clamp)とは、 「かすがい」「締め金」といった名詞と、「留める」「きつく締める」といった動詞の意味があります。
クランプと呼ばれるものには、形状や構造が異なるさまざまなタイプがあります。
建築現場などで運搬に使われるもの、材料を作業台に固定したり、複数枚の材料を圧着したりするときに使われるもの、足場など単管パイプを組み立てる際に使われる結合金具、「かすがい」と呼ばれる、木材などを接合する際に用いる繋ぎの金具などがあります。
用途別に、さまざまなクランプの使い方、注意点などを見ていきましょう。
2章:クランプの種類
主に建築・土木作業・運搬などに使われるクランプ
- ・吊りクランプ
- 吊り上げる荷物の重さを利用し、てこの原理で荷物を挟みます。荷物の重みでクランプの吊カンが引っ張られると、クランプのカムと呼ばれる歯が荷物に噛み込むクサビ作用が働き、荷物をより強く挟みます。カムは、縦吊りで約1.6倍、横吊りで約1.0倍の吊荷荷重で支えることが可能です。
- ・パイプクランプ
-
屋内外を問わず様々な場面で役に立つ、単管パイプ組み立て用のクランプです。
足場を組み立てるときなどに、単管パイプを交差または平行して結合させるために用いる緊結金具です。ジョイントで繋ぐことで、長い直線を作ることができます。
単管パイプを使った構造物は簡単に組み立て・解体ができるので、DIYでもよく使われます。 - ・鉄骨クランプ
- 鉄骨に単管パイプやネット、チェーンなどを安全に繋ぐためのクランプです。
主にDIY/木工・鉄工作業などで使用するクランプ
DIYや木工・鉄工作業などで使うクランプは、材料を作業台に固定したり、材料同士を圧着するときなどに使う、締めつけのための道具です。
作業の際、材料を安全に押さえることができ、材料同士の圧着時には、接着剤が硬化するまで材料を固定しておくのに使用します。
材料を挟んで固定するための作業工具には「万力」や「バイス」と呼ばれる作業工具もありますが、こちらは、材料同士を繋ぎ合わせるために使うことはありません。
「万力」「バイス」は材料が動かないように固定する作業工具、「クランプ」は作業台と材料、または材料同士を固定するための作業工具と考えるのがわかりやすいでしょう。
作業用クランプは用途に応じてさまざまなものがあります。用途別のクランプの選び方は第4章で説明します。
3章:クランプの許容荷重
足場用の単管パイプクランプ許容荷重(スベリ荷重) は、メーカーなどによって異なりますが、単管クランプの許容荷重は概ね、1個当たり直交で500kg前後、自在で300kg前後です。
鉄骨クランプの許容荷重はクランプの大きさや取りつけ方法によって異なります。工業会認定基準は6.18KN以上となっています。
4章:用途別クランプの選び方
主に建築・土木作業・運搬などに使われるクランプ
- ・吊りクランプ
-
鉄鋼用クランプは、鉄などの金属でできたさまざまな形状の材を吊り上げるためのクランプです。縦吊り、横吊り、縦横兼用型、ねじ式、水平式などの種類があります。
コンクリート二次製品用クランプは、U字溝・側溝・基礎ブロックなどのコンクリートを吊り上げるクランプです。
そのほか、石材吊り用クランプ、建設作業用クランプ、土木工事用クランプなど、吊り上げる荷物の形状・用途に合わせてクランプのタイプを選んでください。 - ・パイプクランプ
-
単管パイプ組み立て用のパイプクランプには、直交型クランプ、自在型クランプ、三連クランプなどがあります。それぞれに適合するパイプのサイズがあるので、用途と使用するパイプの直径に合わせて選びます。パイプの直径を兼用するタイプもあります。
直交型クランプは、直交するパイプの緊結に用いるもので、パイプの交差角度を直角に保持させる構造になっています。
自在型クランプは、交差する2本のパイプの交差角度を自在に変えられる構造になっています。
三連クランプは、パイプを3本連結させるときに使用するクランプです。柱となるパイプに2本のパイプを交差させる形で緊結します。三連直交クランプは、2本のパイプが直角に緊結でき、もう1つのパイプは自由な角度で緊結できるようになっています。三連自在クランプは、3本のパイプが自由な角度で緊結できるようになっています。
主にDIY/木工・鉄工作業などで使用するクランプ
ネジを打ったり、木材を切ったり、接着したりする作業が多いDIYでは、クランプはそのさまざまな場面において、効率的かつ正確な作業を手助けする便利な作業工具です。
- ・C型、B型クランプ
-
C型は最も一般的なクランプで、シャコ万力とも呼ばれます。締めつけ力が強力です。B型は「BAHCO(バーコ)」社が最初に作ったタイプのクランプで「バーコ型」とも呼ばれます。
C型クランプとB型クランプはよく似た形をしていますが、B型クランプに比べC型クランプはフトコロ(奥行)寸法が広いので、材料をより深く挟み込むことができます。 - ・F型クランプ
-
L型クランプとも呼ばれます。バーの長さもサイズが豊富で、開口の広いものを選べば、長いものも挟むことができます。締めつけも強力で作業性も良く、価格も比較的安価なので、DIY初心者にオススメのクランプです。
作業台に固定した時、頭の出る部分が少ないので、電動工具のモーターなどが当たりにくく便利です。 - ・パイプクランプ
- 大型家具など材料が長い場合に使うクランプです。使用するサイズのパイプをクランプの穴に通して使います。長さのあるクランプは収納に場所を取りますが、パイプクランプを使えば、分解できるので便利です。
- ・トグルクランプ
-
「トグル」とは、ハンドルやスイッチ、ボタンなどで操作を繰り返すことで、2つの状態(オン/オフや締める/緩めるなど)が交互に入れ替わる仕組みのことです。
トグルクランプは、木ネジなどで作業台に取りつけて使用するクランプで、このトグル作用とてこの原理を使って人の力でも簡単なレバー作業で強力な締めつけをすることができます。
立型、横押型、横型、水平型、ロングアーム、二股タイプ、引止め方などがあり、用途に合わせて使い分けます。 - ・コーナークランプ
- 木材を直角に固定する際に使うクランプです。45度に切断された材料を使って額縁や木枠などを作る際によく使われます。素材はアルミダイキャスト、アルミ合金、アルミ鋳造など軽くて丈夫なアルミ製が多く、ABS素材などのプラスチック製もあります。
- ・ベルトクランプ
- 木工作業で枠などを作るとき、同時に4隅を固定したいときに使用します。四角形以外に、多角形、丸型などの締めつけにも使用できます。
- ・スプリングクランプ
- バネクランプとも呼ばれます。洗濯バサミと同じような形状で、薄手の板などを挟んで固定する際に使用する作業工具です。物を挟む口金が可動するようになっているものは、材料を水平に保つことができます。脱着が早くスムーズに固定することができるのが特長です。金属製のものと樹脂製のものがあり、グリップ部分にロックレバーがついていると比較的簡単に握ることができます。締めつけ力が弱いので作業台と材料の固定には向きません。材料同士の圧着や仮押さえなどに使います。
- ・ラチェット式クランプ
- ラチェットバークランプ・クイックバークランプなどと呼ばれるクランプです。ハンドルがレバー式になっていて、握ると口が閉まっていき、ボタンを押すと解除する仕組みになっています。片手で材料を固定できる点と、材料を締めつけるだけでなく押し広げることが可能な点が特長です。
- ・ハタガネ
-
締めハタ・旗金などとも呼ばれる、日本に昔からある木工締め具です。
形はF型クランプに似ていますが、F型クランプより開口幅が広く、フトコロ寸法が短くなっています。ハタガネは、材料を作業台に固定するよりも、板の剥ぎ合せなどの際に、材料同士を固定するのに適しています。
5章:クランプの使い方
主に建築・土木作業・運搬などに使われるクランプ
- ・吊りクランプ
-
作業内容に合わせた適切な吊りクランプを選ぶようにします。使用するクランプの種類やメーカー、材料の吊り方などによって使用方法が異なるため、必ず取扱説明書等を熟読し、理解しておくことが重要です。
複数のクランプを使う場合は、タイプの違うものの使用は避け、同一種類のものを使います。木質梁を吊り上げる木質梁吊り用クランプや、建物の外壁用パネルを吊り上げるパネル吊りクランプは、2台1組で使用するとされています。 - ・単管パイプクランプ
-
組み立て・解体が簡単な単管パイプを使って、棚や手すり、ちょっとした物置や屋外の日よけなどが作れます。
ラチェットレンチやインパクトドライバーなどを使うと、ナットやボルトを強力に締めつけられるので安全です。水平器を使って、パイプの垂直・平行を確かめながら組んでいきます。直交クランプで枠を組み、自在クランプを使って筋交いを入れて骨組みを補強させます。筋交いを入れないと倒壊の恐れがありますので、忘れずに使用しましょう。
単管パイプと他の建造物を固定する場合は、キャッチクランプを使います。
主にDIY/木工・鉄工作業などで使用するクランプ
- ・C型、B型クランプ
- ハンドルを回して開口し、材料や作業台を挟んで、ハンドルを回して締めつけます。締めつけが強力なので、直接挟むと材料を傷める場合があります。材料とクランプの間に当て木等をすると材料を傷めません。
- ・F型クランプ
- ハンドルを下げて材料と作業台を挟みます。ハンドル部分を上にスライドさせて、材料や作業台の間際まで移動させ、ハンドルを回して締めつけます。
- ・パイプクランプ
- クランプの2つのパーツの丸穴にパイプを通して材料を挟み、締めつけます。必要な長さのパイプを用意すれば、長いクランプを作ることが可能です。
- ・トグルクランプ
- クランプを作業台に固定した状態で使用します。レバーを動かして開口部を開き、材料を挟んでレバーを倒して締めつけます。
- ・コーナークランプ
- 材料をクランプに挟み込み、ハンドルを回して固定します。箱や額縁などの枠の四隅を同時に固定する場合は、クランプが4つ必要になります。
- ・ベルトクランプ
-
枠の圧着面を合わせて四隅をクランプで挟み込み、ハンドルを回したりラチェットを握ったりしてベルトを締めつけ、材料を固定します。
多角形、円形の場合はクランプのアゴ部分を取り外して、ベルトのみで締めつけ固定します。 - ・スプリングクランプ
- 洗濯ばさみや布団バサミと同じ要領で、握って開口し、材料を挟んでから手を離して固定します。
- ・ラチェット式クランプ
-
ボタンを押して解除し、開口したバーの部分に材料を挟み、ハンドルを握って強く締めつけます。
押し広げる場合は「アゴ」と呼ばれる、材料を挟む部分の部品にある止めネジを緩めてアゴを取り外し、反対向きに取りつけ、ハンドルを握ってバーを開き押し広げます。 - ・ハタガネ
- 頭部分についている締めつけネジと下側のアゴについている固定ネジを緩めて開口し、2つのアゴの間に材料を挟んでアゴを締めます。固定ネジを締めつけてから、締めつけネジを回して固定します。
6章:使い方の注意点
主に建築・土木作業・運搬などに使われるクランプ
- ・吊りクランプ
-
安全性と簡単な作業性を兼ね備えた安全吊具としても使われていますが、反面、誤った使い方や、点検不良により重大な事故に結びついてしまう可能性があります。
正しい使用方法を理解し、注意事項を確認して、安全に使うことが大事です。
【 禁止事項 】
- ・2枚以上の重ね吊り、横つかみ、長尺物の1点吊り
- ・偏荷重
- ・玉掛け作業以外での使用
- ・無資格での玉掛け作業
- ・吊り下げ物の落下範囲内に立ち入ること
- ・つかみ部の勾配が10度以上のもの、つかみ部が滑りやすいもの
- ・150度以上、-20度以下の高温・低温の吊荷
- ・改造や加熱
- ・オペレータ側向きに取りつけた形態であるバックホーでの使用
- ・引きずり作業
- など
クランプを使用する際は、必ず使用前に点検し、異常があるものは使用してはいけません。
また、本体に記載された使用荷重の範囲を超えるものや、極端に薄いものは吊ることができません。
主にDIY/木工・鉄工作業などで使用するクランプ
材料に接する部分が固い素材のものや狭い(小さい)クランプは、材料が滑ったり、凹みや傷などがつく原因になります。締めつけ力の強いクランプを使用するときは、締め口と材料の間に当て木をするようにすると、材料を傷めることなく締めつけることができ、ゴムなどの滑りにくいものを当てると、締めつけた材料が滑りにくくなります。アゴ部分がゴム製のクランプもあります。
材料や治具を作業台などに固定する場合は、クランプを2ヶ所以上使って固定します。1ヶ所の固定のみだと、材料が作業中に回転してしまったり、滑って動いたりして危険です。
クランプの種類によって、口の開きやフトコロ寸法に限度があるので、挟める材料の厚みや幅に注意が必要です。
まとめ
「クランプ」と一口に言っても、使う場面や目的・用途、大きさや形など、さまざまな種類のものがあります。
建設現場などで使うような大型のクランプ、足場や仮設などで使う金物のクランプ、木工作業などで使う作業工具のクランプ、形や用途は全く違いますが、どれも大きなホームセンターなどで購入することができます。
使用する目的や安全性などをしっかり確認して、適切にクランプを選びましょう。