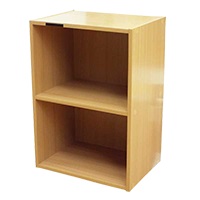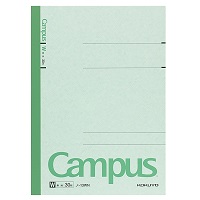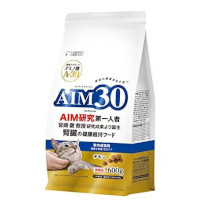土にはさまざまな種類があり、植物によって相性が異なります。園芸用にブレンドされた培養土であればそのまま使えますが、単体用土は植物にあわせてブレンドする必要があります。植える植物の生育に適する用土を選び、複数の土をブレンドする「土づくり」は園芸の基本です。よく使われる土の特質を知って、家庭での園芸にお役立てください。
基本用土とは
用土として配合する割合が多く、つくる土の目的や方向性を決めるベースとなる土です。通気性や排水性、保水性、保肥性、酸度などの特長で使い分け、配合する割合を植物の好みに合わせて調整するのが土づくりの一般的な方法です。
主な基本用土の種類と特徴
●赤玉土もっともよく使われる基本用土です。火山灰土が粒状になったもので、通気性や排水性、保水性、保肥性のバランスがよいのが特徴です。肥料成分を含まない清潔な弱酸性の土であるため、幅広く植物に使うことができます。

●鹿沼土黄色粒状の土で、通気性、保水性に優れた無菌、無肥料の土です。やや酸性のため、サツキやブルーベリーなどの酸性を好む植物に適しています。

●黒土有機質に富んでフカフカした土で、保水性、保肥性に優れ、乾燥を嫌う植物や柔らかい土で育てたい根菜類に向きます。通気性、排水性が悪いため、赤玉土や腐葉土などを混ぜて使います。

●川砂通気性、排水性がよいため、水はけを好む植物に使います。保肥力がないため、赤玉土などに1~2割ほど混ぜて使うのが一般的です。サボテンや多肉植物、盆栽などに向きます。

●水ごけ保水性は抜群。通気性と保肥性にも優れ、ランや山野草、観葉植物、多肉植物の植え込みに向きます。軽さをいかしてハンギングにも使われます。

改良用土とは
ベースとなる基本用土に混ぜて、通気性、排水性、保水性、保肥性などを改善し、より植物の生育に向く土にするためのブレンド材です。腐葉土や堆肥などの有機質のものは、土中の微生物の働きを活発にして、土を肥沃にします。また、無機質のものは清潔なため、室内園芸に広く使われます。このほか、土の保肥力を高められるゼオライトなども、土壌改良材として利用できます。
改良用土の種類と特徴
●腐葉土広葉樹の落ち葉を腐敗、熟成させたもので、通気性、排水性、保肥性に優れた代表的な有機質の改良用土です。赤玉土との組み合わせは、多くの植物に適し、もっともよく使われるブレンドです。

●堆肥樹皮や牛ふんなどの有機物を発酵させたもの。通気性、排水性に優れ、肥料効果もあり、土壌改良にも有効です。原料によってさまざまな種類があり、期待する効果によって使いわけます。

●ピートモス湿地帯に堆積した水ごけが分解し、泥炭化したもの。強酸性のため、土を酸性に傾けたいときに使います。

●くん炭/もみ殻くん炭ヤシガラやもみ殻などを炭化させたもの。アルカリ性のため、酸性土を中和するのに有効です。

●バーミキュライトひる石という鉱物を焼成してつくられた無機用土。通気性、保水性、保肥性に優れているうえ、無菌で軽いという特徴があります。単体で、さし木や種まきの用土としても使います。

●パーライト真珠岩を焼成した無機用土です。通気性、排水性に優れますが、保水性、保肥性では劣ります。非常に軽量で多孔質であるのが特徴で、軽くしたいプランターやハンギングの土へのブレンドに適します。

まとめ
「花づくり、野菜づくりは、土づくりから」といわれるほど、土は園芸でとても重要な要素です。ブレンド済みの培養土は手軽さが魅力ですが、単体用土を自分でブレンドするのであれば、植物ごとにきめ細かく対応することができます。また、改良用土を使って市販の培養土を調整することもできます。いろいろと工夫をしながら、ご家庭での園芸を楽しんでください。