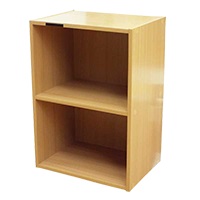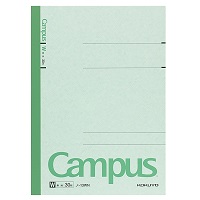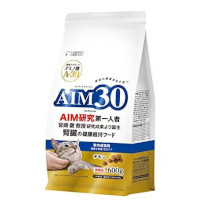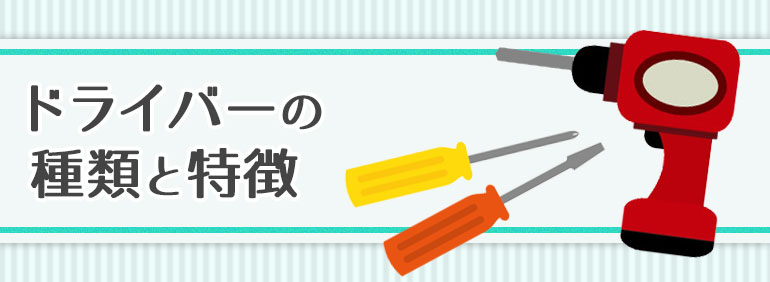目次
1章:ドライバーの基本
2章:ドライバーの使い方
3章:プラスとマイナス、刃先の違い
4章:ドライバーの種類
まとめ
通販で購入した家電や家具などの組み立てから、自転車やバイクなどのちょっとした整備、また棚などの緩んだネジを締めるなどの際にも欠かせない工具がドライバーです。おそらくドライバーを使ったことがないという人はほとんどいないのではではないでしょうか。
スパナやレンチなど工具にはもちろんほかにも様々なものがあります。しかし、こういったものは意外に使う機会が多くないものです。日常的に使う工具といえば、やはりドライバーが一番でしょう。
どちらの家庭でも何本かはきっとどこかにあるはずです。それは、もしかしたら組み立て家具などに付属していた簡易的なものを、そのまま日常に使用されているのかもしれません。
また、DIYを趣味にされている方なら本格的な電動ドライバーやインパクトドライバーなどまでそろえているということもあるかもしれません。
そんな、誰もが一度は手にした事のあり馴染み深い工具の代表であるドライバーについて、その種類の違いや正しい使い方、さらに選び方のコツなどについてご紹介します。
1章:ドライバーの基本
日常のちょっとした作業に欠かせないドライバー
部屋の中をちょっと見回してみるだけで、家電や家具、自転車や機械部品など様々な場所に使われているのがネジ(ビス)です。ネジは、わざわざ説明するまでもありませんが、らせん状のネジが切られたネジ穴に差しまれ、回転して部品同士を締め付けることでパーツを固定したり繋いだりする固定具です。そして、そのネジを回し、締め付けたりゆるめたりするためのツールがドライバーです。
ドライバーは英語ではScrewdriver(スクリュードライバー)といいます。ドライバーは和製英語で、英語圏の方には例えばプラスドライバーやマイナスドライバーといっても通じないそうです。ちなみに英語では、プラスドライバーはCross-head screwdriver、マイナスドライバーはStraight-head screwdriverというのだそうです。
そんなドライバーですが、一般的なものはグリップの中心を貫くように金属製のシャフトが固定されており、その先端のネジを回す部分が十字状や-字状、星型など様々な形になっています。
そして、その先端の形によって、プラスドライバーやマイナスドライバーなどと日本では呼ばれています。
歴史的には先にマイナスドライバー(及びマイナスネジ)が誕生しその後にプラスドライバー(及びプラスネジ)が誕生しました。アメリカではプラスネジが戦前から普及していましたが、日本では戦後JIS規格が制定された1949年からようやく使用されるようになったそうです。ちなみにプラスネジを日本で本格的に導入したのは、自動車メーカーのホンダだといわれています。
マイナスドライバーとプラスドライバーは単純にその形が大きく違いますが、それによって作業効率も違ってきます。ドライバーとネジの部分の接触する部分が多い分プラスの方がスリップ(滑ってしまう)する事が少なく、より回しやすい上に強く締め付けることができ、また最大でも45度回転(マイナスネジは最大で90度)させるだけでネジ溝のドライバーの刃がかみ合ってくれるます。
また、プラスなら多少ドライバーが斜めに差し込まれても刃がかみ合い(マイナスは真上から溝に刃を差し込まないとネジを回すことが難しい)力が伝わるので、作業もスムーズに行えます。そのため電動ドライバーにも適しています。そのため現在では世界中で使用されているネジの約9割がプラスネジだといわれています。
ではなぜマイナスネジが残っているのか。それは、プラスネジは一度溝に汚れがつまったりすると、取れにくくそれが原因でサビてしまう可能性があるため。汚れがつきやすい場所では、比較的簡単に汚れをかき出せるマイナスネジをあえて使用していることもあるのだそうです。
また、装飾的な意味でもマイナスネジはプラスネジよりも高級とされています。そのため、デザイン的にネジの頭が見える家具や機械類ではあえてマイナスネジを採用しているものも少なくありません。
さらに、高級な機械式腕時計などでも、使われているネジのほとんどがマイナスです。このようにプラスネジが主流になった現在でも、まだまだマイナスネジの需要があり、そのためにマイナスドライバーのニーズもあるのです。
このようにプラスドライバーが主流となった今でもまだまだマイナスドライバーを使用する機会もあるので、ドライバーはプラスとマイナスをセットでそろえておくべきなのです。
ただし、マイナスドライバーに関して、一点注意があります。それは業務やその他の正当な理由がないのに持ち歩いていると処罰の対象になってしまう可能性があるということ。なぜならば特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(ピッキング防止法)の「指定侵入工具」に、マイナスドライバーが指定されているからです。
もちろん正当な理由があれば問題ありませんが、何かあった時のため、など正当な理由なくマイナスドライバーをバッグなどに忍ばせておくと、職務質問などにあった際に処罰されてしまうこともありえるで注意してください。
2章:ドライバーの使い方
押す力が7、回す力が3が基本
ドライバーの選び方の基本は、当たり前です使用するネジのサイズにあったドライバーを使うことです。マイナスネジもプラスネジも、多少サイズが合わなくともある程度回せてしまいますが、合わないドライバーを使用すると力がキチンと伝わらずネジをなめてしまうこともあります。
もしネジのサイズが分からないという時は、最初にそのネジのサイズより明らかに大きいと思われるドライバーを試してください。
そのドライバーが合わなかったら、次にその下のサイズのドライバーをあわせてみます。それで先端がネジにぴったりと合うものがあったら、そのドライバーが正しいサイズです。作業をはじめましょう。
ドライバーの使い方の基本は、押す力7に対して回す力3で回します。ネジに対してドライバーの刃先を押し付けるようにしながら回すのです。回す際には軸がぶれないように、両手を使って軸にも手を添えるのがポイントです。片手で使用すると、ドライバーの軸がぶれてしまうため、ネジをしっかりと締めることができません。
もしネジが軽く回る場合は、押す力を弱め、逆に固く回りにくい場合は押す力を強くするといいでしょう。固く締まったネジを緩めるときは、回す力よりも意識して押す力を強めないとネジをなめてしまうこともあるのでくれぐれも気をつけてください。
もし、家具の組み立てなどでたくさんのネジを使う場合や、ネジ締めにより大きな力が必要な場合は、手動タイプではなく電気などの動力で動く電動ドライバーを使うといいでしょう。その際、あまり回転を速くせず、ゆっくりと締め付けることをこころがけましょう。また、手動のドライバーと同じで押し付ける力を意識してください。押しつけが弱かったり、回転が速すぎるとネジをなめてしまうことがあります。注意しましょう。

サイズの合わないドライバーの使用はネジをなめる危険性があります。必ずネジのサイズにあったドライバーを使用し、ネジに対してドライバーを真っ直ぐに立てるようにします。またネジを押し付ける力7に対して回す力3が基本です。
3章:プラスとマイナス、グリップの違いなど
サイズが合わないとネジをなめることも
ドライバーの中でも最も一般的なのが、十字の溝が切られたネジを回すためのプラスドライバーです。工具売り場などに行くと、長さや大きさなど様々なプラスドライバーがあります。そしてプラスドライバーは刃先のサイズがJIS規格によって明確に決められています。
サイズにはNo.0、No.1、No.2、No.3と4つがあり、一般的に使用されることが多いのがNO.2です。もし最初の一本としてドライバーを購入するという場合は、このNO.2を購入するといいでしょう。そして、このNO.2中心にNO.1、NO.3をあわせ3本揃えておくと、たいていの事に間に合うはずです。
もう一つの代表といえるドライバーがマイナスドライバーです。こちらはシンプルに先端がマイナスの形になっています。JIS規格では刃幅と軸の長さで区別されていますが、ドライバーの刃がネジの溝と合っていれば多少サイズが違っても一本で様々なマイナスネジが回せます。
しかし、あまりにサイズが違っているとネジをなめてしまうこともあるので注意しましょう。マイナスドライバーを購入するならば、刃幅が3ミリのものと、5.5ミリか6ミリ、そして7ミリか8ミリのものの、計3本ほど揃えておくといいでしょう。
マイナストライバーはその先端が刃物のようにも見えるため、ついグリップのお尻部分をハンマーで叩きタガネのように使ってしまったり、テコのように固くしまった蓋などをこじ開けるのに使ったりしてしまいがちです。
しかし、ドライバーはあくまでネジを回すための工具。あまり乱暴に扱うのはやめましょう。軸や刃先を傷める原因になります。ただし貫通型のドライバーを使い、固く締まったネジを緩めるためにグリップのお尻の部分を叩くのは問題ありません。

プラスドライバー。
刃先のサイズは、No.2を中心にNo.1とNo.3などあわせて3本ほどそろえておくとほとんどの用途に間に合うはずです。

マイナスドライバー。
幅が多少合わなくてもネジを回せてしまいますが、刃幅が3ミリのものと、5.5ミリか6ミリ、そして7ミリか8ミリのものの、計3本ほど揃えておくのがオススメ。
● 貫通型と非貫通型とは
見た目では分かりにくいのですが、ドライバーには貫通型と非貫通型という構造の違いがあります。その差は軸の取り付け方です。一般的なのは非貫通型です。グリップ部分に、先端に刃が刻まれた軸(シャフト)が差し込まれているという点は同じですが、非貫通型はシャフトがグリップの途中までしかありません。もちろんこれでドライバーとしての機能はまったく問題ありません。
それに対して貫通型は軸がグリップを貫き、グリップの底部分がその軸と繋がる座金になっています。つまり、軸の片側が刃先、反対の端が座金となっていて、その軸に巻きつくようにグリップが設けられているということです。貫通型は、軸がグリップを貫通し、座金もあるので同じサイズでも重さ的には重くなってしまいますがその分強度が非常に高いのが特長です。
もしネジなどが固着して動かないときなどは、ドライバーをネジに差し込んだ状態でこの座金部分をハンマーなどで上から叩きます。こうすることでネジに直接ショックを与えることができ、動かないネジを緩めることができるのです。ただし、その用途からドライバー先端の劣化が早くネジなどを傷める可能性があるということも頭にいれておきましょう。貫通ドライバーでも緩めることのできないネジはインパクトドライバーも試してみてください。

貫通ドライバーはこのようにグリップを軸が貫通し、底部分が頑丈な座金になっています。ここをハンマーで叩くことで固着したネジに打撃を与えて緩めることが可能です。
● グリップの違い
ドライバーはグリップにも違いがあります。メーカーによって様々な材質が使用されています。使われている材質の特性によっては作業のしやすさも変ってきますので意外に重要です。代表的なものは樹脂製、いわゆるプラスチックですが、樹脂性のものにも硬いハードタイプと、弾力のあるソフトタイプがあります。
ハードタイプは耐久性が高く、また汚れにも強いのが特長です。ソフトタイプは手に優しくまた滑りにくいのが特長です。さらに力をいれても疲れにくいため、長時間の作業にも適しています。ただし、汚れやすいのが欠点です。
手触りが良く質感も高いということで高級なドライバーには木製のグリップもよく使用されています。油で汚れた手でもグリップが滑りにくい上、コーティングされているものなら汚れにくいという利点もあります。
またサビに強く汚れにくいということから金属のステンレスをグリップに使用したものもあります。重量バランスが手元のグリップ側にくるため、力をいれやすいのがメリットですがその分重くなってしまいます。
このようにグリップの素材によって、使いやすさなどが変ってきますが、購入の際は、実際に売り場などで握ってみて、自分に使いやすいものを選ぶと良いでしょう。その際は、素材だけでなく、グリップの断面形状(丸や六角、四角など)にも注目してみてください。
4章:ドライバーの種類
用途に合ったドライバーを選ぼう
プラスネジやマイナスネジはそれにマッチしたドライバーを使用することで、締め付けたり緩めたりすることが可能です。しかし、作業の目的によっては一般的なプラスやマイナスドライバーではうまく作業が出来ない場合もあるでしょう。そんな時は特別な機能を持ったドライバーを別途用意し、そちらを使ったほうが安全かつ効率的に作業を行うことが可能です。
例えば全長の長いドライバーが入らないような、棚の奥などの狭い場所のネジならば、全長の短いスタビードライバーが向いています。無理にナナメにドライバーを差し込むとネジを傷める可能性があるので、スタビードライバーを使用しましょう。
また、固着して動かなくなったネジを緩めたいなら貫通ドライバーを使うと良いでしょう。無理に力を加えてネジをなめてしまう前に、ハンマーでネジに打撃を与えてから固着を解消し回すことで緩められる可能性が高まります。
六角のヘックスネジや、星型のトルクスネジなど、プラスやマイナス以外のネジにはもちろんそのための専用のドライバーが必要です。あまり一般的ではありませんがホームセンターなどにはサイズごとに専用のドライバーが用意されています。
ネジのサイズが分からない場合は、六角のヘックスネジの場合なら六角形の直線の辺とその対辺までの長さを測ります。トルクスの場合は星型の頂点とその反対側の頂点までの長さを測ります。このサイズを売り場などでお伝えるとマッチしたドライバーを見つけることができます。
合わない工具を無理に使うことは極力避けてください。特殊なネジには面倒ですが、専用のドライバーを使用するようにしましょう。合わない工具の使用は思わぬ怪我に繋がることもあります。気をつけてください。
● スタビードライバー
通常のドライバーよりも軸、グリップ共に小型で全長が短いドライバーがスタビードライバーです。通常のドライバーが入らないような隙間などの狭い場所の作業に適しています。逆に手の届かない場所の作業にも適したシャフト部分の長い長軸ドライバーというものもあります。

● 電工ドライバー
ハンドルが丸く大きくなっており、手のひらで包み込むように握ることができるのが電工ドライバーです。回す時に力が入れやすくデザインされています。電気工事作業などに使われるドライバーですが、もちろん通常の作業にも使用可能です。

● ラチェットドライバー
グリップとシャフトが固定されておらず任意の一方向(回転方向は切り替えが可能)の回転時にしか力が伝わりません。力を伝えたい方向とは逆にグリップを回転させた際は先端の刃先は動かずにグリップ部分だけが回転してくれるので、グリップを持ちかえることなくスピーディに作業が行えます。

● マグネット入りドライバー
作業中にネジが落下しないように、刃先の部分に磁力を持たせたドライバーです。

● ソケットドライバー
プラスやマイナスではなく、六角ボルトやナットを回すための専用ドライバーです。スパナやレンチよりも大きな力を伝えることは難しいですが、その分スピーディな作業が可能です。

● ヘックスローブ(トルクス)ドライバー
穴の部分が星の形をした、T型ヘックスローブ(トルクス)ネジやボルトを回すためのドライバーです。効率的に力を伝えることができる上、磨耗や割れにも強く耐久性も高いという特長をもっています。T型トルクスネジの中央部に丸型の突起物があるものは、いじり止めトルクスネジと呼ばれ、ドライバーも中央部に穴のある専用のヘックスローブ(トルクス)ドライバーが必要です。しかし通常このネジが使われているのはメーカーも分解を推奨しないみだりにネジをゆるめるべきではない箇所です。手を触れないのが懸命です。

● インパクトドライバー
貫通式ドライバーと基本的な用途は同様です。違いは先端が打撃によって回転すること。グリップ部分の座金をハンマーなどで叩くと、その衝撃を回転力に変えて、締め過ぎたり、固着したネジを緩めることができます。

● 精密ドライバー
メガネや精密機器などの小さなネジの締め付けや、取り外しに使用します。

● 電動ドリルドライバー
動力に電気を使用し、ネジを締めたり緩めたりするほか、先端のビットを交換することで穴あけ作業も行えるのが電動ドリルドライバーです。電源にはコード式とバッテリー式がありコード式はパワーが安定しているというのがメリットです。しかし、作業場所を移動しながら使いたいという場合にはコードがじゃまになることもあります。その場合は、自由に移動できる充電式バッテリーの電動ドライバーが向いているでしょう。伝道ドライバーは手動のドライバーよりもパワフルですが、締め付ける力を調節することもでき、繊細で正確な作業にも向いています。選び方としては、DIY用であれば、リーズナブルなものでも十分ですが、頻繁に使う予定であれば、パワフルで耐久性にも優れたプロ使用のモノに目を向けてみてもいいかもしれません。

● 電動インパクトドライバー
電動ドリルドライバーと同様に動力に電気を使用するドライバーです。電源は同じようにコード式とバッテリータイプがあります。電動ドリルドライバーとの大きな違いは、回転と同時に打撃力を加えることができるという点です。そのため、固く締まったネジを緩めたり、厚い木材に長いビスを打ち込むなどパワフルな作業にも向いています。しかし、電動ドリルドライバーとは違いトルクの調節機能がついていないので、小さいネジ締めなどの細かく繊細な作業には向きません。

まとめ
必要な時に限って中々見つからないことも多いドライバー。だからといって、とりあえず手元にあった、形やサイズが合わないものを無理に使うのは避けましょう。合わない工具の使用はネジをなめてしまいやすく、また、手が滑って怪我に繋がることもあるかもしれません。高価なものではないので、刃先のサイズ別に、信頼できるメーカーのドライバーをそろえておくことをオススメします。
また、ドライバーだけではありませんが、工具は必要な時にすぐに取り出せるように、まとめて一つの場所に保管しておくといいでしょう。