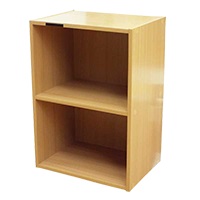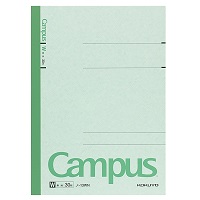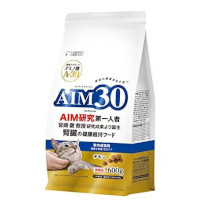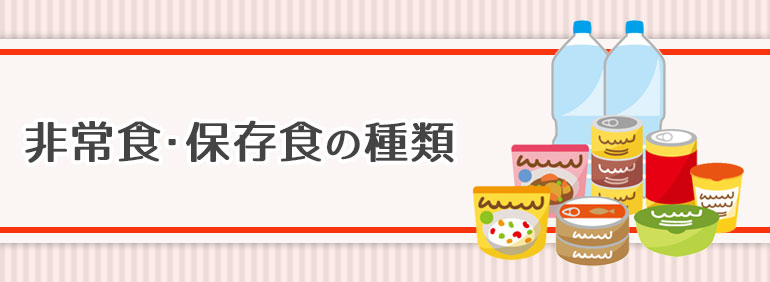自然災害はいつ起こるかわかりません。災害が起こってから支援物資が届くまでには時間がかかります。その間いかに元気に生き延びるかは、個々に用意した非常食にかかってきます。この大切な非常食を備蓄するにあたり、非常食の種類や選び方、ストックの仕方などをわかりやすく説明します。
目次
1章:非常食とは?
1.非常食とは
2.ローリングストック法
3.非常食とともに用意しておくもの
2章:非常食の特徴
3章:非常食の種類
1.主食
2.主菜・副菜
3.お菓子
4.飲料
4章:非常食の選び方
1章:非常食とは?
1.非常食とは
非常食とは災害などいざというときのために保存する、または保存してある食べ物です。避難用防災袋に入れておくものから、家に備蓄して置くものなどさまざまなものがあります。
家庭での非常食の備蓄量は最低3日分、理想的には支援物資が届き始めるまでの7日間分の非常食を備えておく必要があるといわれています。災害当日1日分の非常食はそのまま食べられるものを選び避難用防災袋などに入れておきましょう。
2.ローリングストック法
家族全員分の非常食はかなりの量となり、保存場所の確保や非常食の購入コストもかかります。水だけでも大人1人につき1日3L(飲料1L、炊事、衛生2L)必要といわれています。また非常食にも賞味期限があります。気がつけば賞味期限が過ぎてしまい無駄になってしまったということも考えられます。こういったことを防ぐために日常の食料品を多めに買い、その食料品を使ったらその分を買い足しストックするというローリングストック法が推奨されています。
3.非常食とともに用意しておくもの
大規模災害などによりライフラインが止まると、復旧に時間がかかる場合があります。このようなときにはカセットコンロが役立ちます。お湯を沸かしたり、非常食を温めたり、調理したりと便利なカセットコンロとガスボンベを用意しておきましょう。食品を温めるキットなども用意しておくと便利です。

その他、割り箸、使い捨てスプーンやフォーク、紙皿、ラップ類、アルミホイル、ビニール袋、ウエットティッシュなども非常食と一緒に保管しておくと良いでしょう。
2章:非常食の特徴
非常食の特徴は保存期間(賞味期限)が長く日持ちすること、常温保存ができること、持ち運びやすいこと、手軽に食べられることなどが挙げられます。
日頃食べている食品をたくさん保存していても、いざというときに賞味期限が過ぎていれば使いものになりません。ローリングストックで食品を回しながら使っていても、種類が増えれば大変な労力になります。非常食用として作られている食品は長期間保存できるように賞味期限が長くなっています。例えば、アルファ米の賞味期限は製造日より5年、缶入りビスケットは3~5年、レトルト食品は2~5年、飲料水は2~5年などかなり長く、備蓄しやすくなっています。
非常食では、温めなくても開封するだけで食べることができ、汚れた手でも、また手を汚さずに食べることができること、出るゴミの量が少ないことも大切です。コンパクトで持ち運びやすい非常食は個包装されているものも多く、袋を開けてそのまま口に運ぶことができます。レトルト食品や缶入りのものは湯煎で温めることも可能です。また非常食の中には、自立するスタンドパウチ型になっているものがたくさんあります。お皿や器に取り出さずパウチから直接食べることができます。その他、非常食に箸、フォーク、スプーンなどがセットされているものや、缶切りのいらないプルトップ式の缶詰など工夫もされています。中には、温めキットが内蔵されている非常食もあります。
災害に遭遇したとき、避難場所に避難したとき、自宅で避難生活をするときなど時間とともに必要な非常食のタイプは変わってきます。開封後そのまま食べることができエネルギー補給がしやすいもの、飲料水を使って調理するもの、災害後の少し濁りのある水でも湯煎調理可能なレトルト食品や缶詰などいろいろな種類を備蓄しておくと良いでしょう。
3章:非常食の種類
1.主食
主食とはエネルギー補充のための食べ物です。主食としての非常食にはアルファ米、包装米飯(レトルト米飯、無菌包装米飯)、ご飯の缶詰、乾燥餅、パンの缶詰、乾パン、カップラーメン等があります。
アルファ米は米の70~80%を占めるデンプンに、水と熱を加えアルファ化しさらに乾燥させたものです。このアルファ米にお湯や水を加えて放置するだけでやわらかく美味しいご飯ができあがります。白米だけでなく五目ご飯やピラフなどの味つけご飯もあり、おかずがなくても美味しく食べられる工夫がされています。



個装米飯は電子レンジや湯煎で加熱して食べるパック入りのご飯のことでレンチンご飯、チンご飯とも呼ばれています。レトルト米飯、無菌包装米飯は製造工程の違いで分類されていますが、レトルト米飯の方が賞味期限が長いため非常食に向いていると言われています。
レトルト米飯はレトルト容器(保存安全性が高い特殊フィルム)のままお湯で温めてから食べます。賞味期限は製造日から5年で、災害用・非常用のご飯として販売されています。
レンチンご飯の無菌包装米飯は賞味期限が製造日より10ヶ月ですが、スーパーなどで簡単に手に入るのでローリングストックすると良いでしょう。レンチンご飯は一般的な1パック200g入りに加え、300g入り(特盛)、260g入り(かるく2膳分)、150g入り(少なめ1膳分)、などいろいろあります。また銘柄米、雑穀米入り、おにぎり用、寿司飯用、食事制限用に低蛋白ご飯なども販売されています。
ご飯の缶詰は缶を開けずに湯煎で15分程度温める必要がありますが、製造日より5年間の賞味期限があります。五目飯、鳥めし、牛めし、ドライカレーなどがあり、1缶180g程度ですが、おかずのいらない1食として備蓄に適しています。
乾燥餅は水に1分程度浸すだけで食べることができます。乾燥餅はたくさんのメーカーで販売されていますが、乾燥餅を戻すための水が同梱されているものと同梱されていないものがあるので注意してください。乾燥餅の賞味期限は5年から6年と長く、海苔や醤油の素、きなこ、あんこ、抹茶などのトッピングがついているものもあります。白いお餅はそのまま食べるだけではなく、汁物の具として使うと満腹感も得やすいので他の非常食と組み合わせて使うことをオススメします。
パンの非常食には水分が少なく硬い乾パンや、缶や特殊フィルムで包装されたやわらかいパンがあります。乾パンは1個の大きさや形(四角いもの、ステック状のもの)が違うものなどいろいろあります。乾パンは水分が非常に少ないため飲み物も一緒に摂るよう心掛けましょう。乾パンの賞味期限は包装状態などにより変わります。ビニール袋入りは1年、缶入りは2年から5年とさまざまです。やわらかい非常食用パンは、主にプルトップ式の缶に入っており簡単に開けることができ、すぐに柔らかく美味しいパンを食べることができます。缶入りパンはスコーンタイプ、マフィンタイプ、デニッシュタイプなどがあり、さらに味の種類もプレーン、チョコレート、ミルク、コーヒー、オレンジ、りんごなどたくさんの種類があります。1缶(パン100g)のエネルギー量も350キロカロリー前後と多く、賞味期限も製造後5年となっています。特殊フィルムで包装されたパンは缶入りパンに比べると柔らかさは劣りますが、コンパクトで備蓄しやすく、長期保存(5年)もできるため学校や企業などで多く備蓄されているようです。


通常販売されている便利なカップ麺類、インスタント袋麺類などはスーパー、コンビニなどどこにでも置いてあります。しかも安価で手に入れやすいため日常食としてもスットクされることが多いと思います。しかし、カップ麺や袋麺は賞味期限が製造日より6ヶ月程度と短いため、気がつけば賞味期限が過ぎているということが往々にあります。
カップ麺にも長期保存用があります。缶の中に2食分の麺、スープの素、かやく、紙カップ、折りたたみフォークが脱酸素剤とともに入っており、製造後3年の賞味期限がある保存缶が販売されています。またUAA製法を使って作られた製造後5年という長い賞味期限の非常用ラーメンやうどんもあります。
その他こんにゃく麺を使ったスープ入りの冷たいままでも食べられるラーメン缶(賞味期限3年)もありますが、低エネルギーのため主食よりおかずの1つとして利用しましょう
うどん、そうめん、蕎麦、パスタなどの乾麺は日常的にストックしている家庭が多いと思いますが、乾麺を茹でる際たくさんのお湯が必要です。それらはライフラインが復旧してから使用することになるでしょう。
2.主菜・副菜
主菜・副菜になる非常食には、レトルト食品、缶詰などがあげられますが、非常食用に作られたものから、日常使いのものまでたくさんの種類があります。
非常食用として作られているレトルト食品には、煮込みハンバーグや卵入りおでん、肉じゃが、さばの味噌煮、筑前煮、牛丼の具、カレー、豚汁などがあり、賞味期限は製造後3~5年とメーカーによって違います。これらのレトルト食品はそのままでも食べられますが、湯煎で温めるとさらに美味しくなります。またカレーは冷たいままでもなめらかで油脂の固まりが気にならない工夫がされており、白米とセットになっている便利なものもあります。
賞味期限が5年間ある非常食用おかずの缶詰(さんまの味噌味、牛肉の大和煮、焼き鳥、おでんなど)が備蓄用に作られています。日常使いの缶詰の賞味期限は2年から3年程度と非常用缶詰に比べ短いですが、種類が非常に豊富にあり、しかもスーパーなどで容易かつ安価に手に入ります。そのまま食べられる肉や魚の煮物や焼き物、ひじきや五目豆、きんぴらといった副菜、シーチキンやコンビーフなどの缶詰も非常食用缶詰と一緒にローリングスットクしておくと良いでしょう。
同様に日常使用のレトルト食品などもローリングストックしておくと良いですが、賞味期限が短いものもあるので注意してください。



3.お菓子
調理をしなくても開封しそのまま食べることができるクッキーやビスケット、おせんべいなどのお菓子は、身近な非常食の1つですが賞味期限が6ヶ月から1年程度とあまり長くありません。ローリングストックしやすいものの、気がつけば賞味期限が過ぎていたということも多々あると思います。それらのお菓子の中にも保存缶や特殊フィルム入りの非常食用があります。これらは箱入り、ビニール袋入りの通常販売のものを缶や特殊フィルムの容器に変え賞味期限が製造日より5年と長期保存を可能にしています。その他、缶入りアメ(賞味期限5年)、缶入りキャラメル(賞味期限3年)なども長期保存用に作られています。


日常食事の代わりに食べられることもあるクッキータイプやドリンクタイプなどの栄養バランス食品はコンパクトで持ち運びやすく、食べやすく、保存食にも適しています。通常販売品は賞味期限が1年程度ですが、長期保存用の製造日から3年のものも作られています。このような栄養バランス食品もローリングストックの仲間に入れることをオススメします。

ゼリーや羊羹は賞味期限が1ヶ月から1年と、物によってかなりの差があります。栗などの入っていない煉羊羹は製造後1年程の賞味期限があるので上手くローリングストックの仲間に入れてみましょう。非常食として作られた保存用羊羹『えいようかん』(60g入りのミニ羊羹5本入り)は賞味期限が5年間あります。ミニ羊羹1本で171キロカロリーもあるためエネルギー補給に適しています。
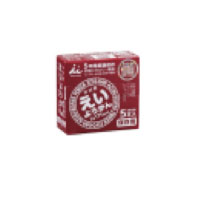
避難生活が続くと日々の非常食にも飽きてきます。そのようなときに一口二口でもデザートを添えることができるとストレス緩和にも役立ちます。常温保存ができるゼリー類やフルーツ缶、みつ豆缶などの缶詰もローリングストックしておきましょう。非常時におせんべいやチョコレートなど食べ慣れたお菓子を食べると、安堵感や安心感を与えてくれると思います。お好みに合わせて可能な限りローリングストックしておくことをオススメします。
4.飲料
昨今、飲料水を購入する家庭が多くなってきたと思いますが、通常販売されている飲料水の賞味期限は2Lボトルで2年程度です。
非常時に必要な水は飲料用と炊事用で1人1日2Lとし、家族4人であれば1日に8リットル、衛生用の水も合わせると4人家族で1日に2Lボトル6本入り1箱分にもなります。これが3日分、7日分、10日分となると日数分の箱が必要となります。
この大量の飲料水は賞味期限2年の2Lボトルや使い勝手のよい500mLボトルをローリングストックしても良いですが、一部を賞味期限の長い非常用備蓄水に変え、残りの通常飲料水をローリングストックするという方法もあります。
非常用備蓄水は通常販売水より少し高価ですが、ペットボトル入り、缶入り、アルミパウチ入りなどがあり、賞味期限は5年から12年、1本の容量は2L、500mL、340mLなどいろいろあります。缶入り、アルミパウチ入りの水はそのまま湯煎で温めることもできます。
飲料水の備蓄は、それぞれの家庭での使い勝手を考えながら通常販売水、非常用備蓄水を併用しローリングストックすることをオススメします。

非常食を食べ続けているとどうしても野菜不足になり、栄養素が偏りがちになってきます。『野菜1日これ1本 長期保存用』(賞味期限は製造日より5.5年)などのような備蓄用野菜ジュースなども一緒にストックしておきましょう。
簡単な調理ができるようになれば100パーセントの野菜ジュースは、スープやリゾットなどの食材としても利用できます。

普段飲んでいる常温保存ができるジュース類、お茶類、栄養ドリンク類も6ヶ月から1年程度の賞味期限があります。少し多めに購入しローリングストックしてみましょう。
4章:非常食の選び方
非常食の選び方で迷うことは、どのようなものをどのくらい用意しておけば良いかだと思います。
農林水産省では日数では最低3日間分、できれば7日間分の食料と水、カセットコンロなどを用意することを推奨しています。また災害発生当日1日分は調理せずに食べられるものを用意することが重要と記載しています。
大規模災害に備え、交通網が復旧し援助物資が広く行き渡るまでの10日間分を備えておくとさらに安心です。
飲料水は大人1につき1日3L必要といわれています。
主食、主菜、副菜、お菓子類などは人によって量や好みが違います。また赤ちゃんや幼児、老齢者、食事制限中の人など、人によって用意しなくてはいけないものが違ってきます。何をどのくらい用意するかの目安として便利な非常食セットを利用すると良いと思います。ドリンクを含めた1人1日分、3日分、7日分の食料セットや、ドリンクなしのセットなど多種販売されています。セットされている食料もご飯、パン、おかず、おやつなど種類も多く飽きない工夫がされています。好みのものがあれば単品販売で追加購入しておくと良いでしょう。

備蓄してある非常食も使い方がわからないと、いざというときに慌てます。必ず作り方や用意するものなどを調べておきましょう。可能ならば試食用に単品で購入し味をみたり、アレンジ料理を作ってみてください。
まとめ
非常食は保管場所の確保や、購入費用が必要です。長期保存可能とはいえ賞味期限もあります。無駄にならないよう非常食リストを作り、普段使っている食品とともに管理しましょう。賞味期限の近づいた非常食を使いサバイバル食の日を作ってみましょう。きっと各々の防災の意識を高めることができると思います。
普段使いの食品と非常食を上手くローリングストックしながら、自分流の備蓄をしてください。