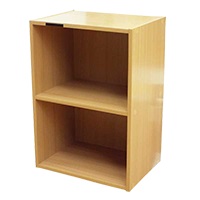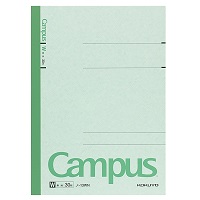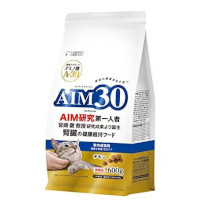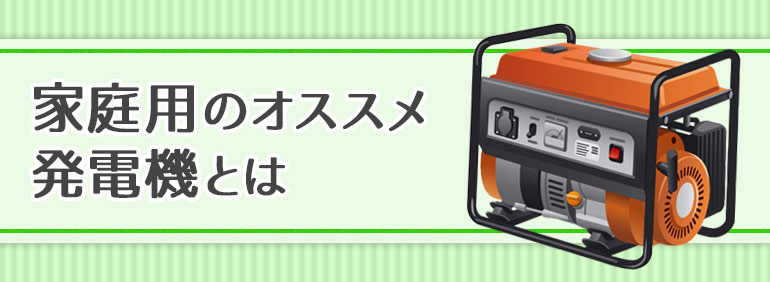目次
1章:発電機とは
2章:インバーター発電機のメリットとは
3章:発電機を選ぶ際のポイント
4章:発電機によって使える燃料が違う
5章:発電機が活躍するシーンとは
まとめ
1章:発電機とは

例えば身近なところでは工事現場やキャンプ場、また、DIYの作業シーンでも見かけることのある発電機。電源が取れない場所で、電気をエネルギーとして使用する機器を使用するために欠かせないものです。
また、最近では仕事や趣味の現場だけでなく防災を目的として、会社や家庭用に発電機を購入されるケースも増えてきているようです。それは手軽に扱えるカセットガス式の発電機が発売されたことも理由なのでしょう。以前よりも身近な存在として注目が高まっているのが発電機です。
そんな発電機ですが、その種類は非常に様々です。大きさ、発電の仕組み、燃料などの違いによっていろいろなタイプが存在しています。しかし、その発電の仕組みは基本的にどれも変わりません。燃料を使用してエンジンを駆動して、磁石またはコイルを回転させることで、電気を起こすというもの。大きなものも小さなものも、ほぼ一緒です。
つまり、自転車のライト用ダイナモから、私たちの家庭に電気を供給してくれる大きな火力、水力発電所まで全て同じ発電機ということになります。
電気がどのように作られているのかは、誰もが一度は実験を行っているはずです。小学生時代の理科の授業などで実験をした記憶はないでしょうか。コイルのそばで磁石を動かすと電気が生まれるという実験です。その原理が電磁誘導で、これがほとんどの発電機に使われている仕組みです。
そして、コイルと磁石を使っている点はモーターと同じとも言えます。実は電気を作る発電機と、電気製品を動かすモーターの仕組みはほぼ同じなのです。その違いは電気を作っているか、使っているかという点だけです。磁石と回転する力などを使って電気を作るのが発電機で、逆に磁石と電気を使って力を発生させているのがモーターということです。
DIYやレジャー、防災用に使われている発電機には主に4つのタイプがあります。それがインバーター発電機とサイクロコンバーター発電機、そしてスタンダード発電機と、三相発電機です。
この中で家庭用の発電機として、使われているのがインバーター発電機やスタンダード式発電機です。しかしポータブル発電機としてはインバーター発電機が主流と考えて良いでしょう。では、どういうものなのでしょうか。簡単に説明します。
インバーター発電機は、従来型の発電機と何が違うのか。まず、いわゆる従来型のエンジンを使用したスタンダード式発電機は、その構造がシンプルなため、小型で信頼性が高いという特長を持っています。また頑丈なため、工作機械や電動工具の電源供給源として非常に優れています。
しかし、エンジンの回転数や電気を供給する際の負荷によって、発電する電気の電圧や周波数が影響を受け、安定した質の高い電気の供給が難しいという大きな欠点を持っていました。
でも、私たちが普段家庭で使用している家電製品は、発電所から供給される安定した周波数を持つ質の高い正確な電気を使用することを前提に作られています。シンプルな単機能の電化製品などなら多少安定していなくても問題ありませんが、コンピューターなどが内蔵された電化製品は、不安定な電気をそのまま使うことができないのです。
日本国内で使用されている電気の周波数は一つではありません。静岡を境に東は50Hz(ヘルツ)の電気、西は60Hzの電気が使用されています。従来型の発電機も、この50Hzと60Hzの周波数を切り替え電気を供給することができるのですが、この周波数はエンジンの回転数でコントロールしていました。そのため、どうしても周波数が安定しないのです。もしも周波数が安定していない電気でパソコンなどの精密機械を動かそうとすると、最悪故障してしまうこともあります。パソコンだけではありません。最近の多くの電化製品、電気機器にはコンピュータが内蔵されているので、そういった機器には従来型のスタンダード発電機は対応できないということです。
そこで登場するのがインバーター発電機です。インバーターとは、簡単に言うと「周波数を安定させる装置」です。インバーターを搭載した発電機ではまず交流で発電します。そして、それをコンバータと呼ばれる装置によって一度直流の電気へと変換します。さらに、それを再びインバーターを使って交流へと変換するのですが、その際に周波数を正確にコントロールすることで質の高い電力の供給を実現しているのです。
つまり、インバーター発電機なら、家庭で使用している安定した電気と同等の質の高い電気を使えるということです。パソコンなどの精密機械の電源としても問題なく使用可能です。キャンプ場で、家庭用のホットプレートや調理家電を使うことも問題ありません。
また、従来型の発電機のようにエンジンの回転数で周波数をコントロールする必要がないので、省エネかつ騒音も小さいというメリットがあります。さらに小型で軽量なので、持ち運びも容易。家庭用としては、とても適した発電機と言えるのです。
ただし、単純な出力では従来型のスタンダード式のほうがパワフルです。またスタンダード式は構造もシンプルな分、耐久性や信頼性が高く、価格的もリーズナブル。もし電動工具などのために発電気が使いたいという場合は、スタンダードタイプの発電機のほうが向いているかもしれません。目的によって選ぶ必要があるのです。
発電機には、ほかには災害時用の手回し式発電機や、焚き火を使って電気を作り出すアウトドア用のストーブなどといったユニークなものもあります。それぞれに特長があるので、どのような目的で発電機を使うのかしっかりと想定してから選ぶのがベストでしょう。もしいろいろな目的に活用したいというなら、汎用的に使えるインバーター発電機が最もオススメです。

2章:インバーター発電機のメリットとは

DIYやアウトドアレジャー、さらに防災用として最も汎用性の高いインバーター発電機。その特長は前述したように従来の発電機よりも、質の高い電気を供給することができるということです。それ以外にもインバーターならではのメリットがあります。そちらを確認してみましょう。
◆ 燃費がいい
従来の発電機のようにエンジンの回転数ではなく、インバーターによって周波数をコントロールできるので、負荷が小さいときにはエンジンの回転数を抑えることができます。そのため燃費に優れています。
◆ 音が静か
動力にエンジンを使用しているので騒音はありますが、スタンダードタイプよりも比較的静かです。機種によって違いますが、その騒音は通常の会話と同様のレベルだとされています。
◆ 対応する電化製品が多い
インバーター発電機なら、周波数の安定した質の良い電気を作り出すことができます。そのため、電化製品やパソコンなど精密機器にも問題なく使用できます。
◆ 持ち運びしやすい
決して軽くはありませんがスタンダードタイプに比べれば軽量設計のものが多いです。大人の女性なら1人でも持ち運べるようなものもたくさんあります。
デメリットとしては、従来型の発電機に比べると価格が比較的高いということでしょうか。また出力が高いものになると重量もかさみます。
ほかには燃料が必要というのもありますが、これはエンジンを使用した発電機なら全てに当てはまることです。実際に購入する際は発電機に繋いで使用する電動工具や電化製品などの消費電力を確認することも大切です。
出力可能な電力よりも消費電力のほうが高ければ、電化製品は正常に動きません。場合によっては故障の原因になるので注意してください。
3章:発電機を選ぶ際のポイント
インバーター式発電機にもさまざまな製品があります。まずはどのような利用シーン、環境で使うのか、さらに、どんな電化製品を繋ぎたいのかなどを考えましょう。
インバーター発電機であれば、もちろん一般的な電化製品やパソコンなどの精密機械、さらに電動工具などにも対応できます。しかし、複数の機器を接続しようとした場合には、使用する発電機の定格出力によっては電力供給が間に合わなくなってしまうこともあります。そのため、発電機で使用する電化製品の起動電力と消費電力のワット数をあらかじめ把握しておく必要があります。
注意が必要なのは、モーターを動かす電気機器によっては、動き始めるときに通常の消費電力よりも大きな起動電力を必要とする製品があるということです。
起動電力とは電気を必要とする機器が、起動するために必要とする電力のことです。消費電力はその機器が動き続けるために必要な電力になります。この起動電力は機器によって大きく変ってきます。ものによっては表示されている消費電力の3~4倍もの電力が必要になることもあるので、注意しなくてはなりません。
◆ 消費電力と起動電力
代表的な電化製品の消費電力と起動電量の例は以下の通りです。
・
ノートパソコン 消費電力(200W)/起動電力(200W)
・
テレビ(37型) 消費電力(300W)/起動電力(300W)
・
コーヒーメーカー 消費電力(650W)/起動電力(650W)
・
ハロゲンライト 消費電力(250W)/起動電力(500W)
・
電子レンジ 消費電力(1000W)/起動電力(1800W)
・
電動ドリル 消費電力(300W)/起動電力(600W)
・
インパクトレンチ 消費電力(500W)/起動電力(1000W)
・
エアーコンプレッサー 消費電力(750W)/起動電力(3000W)
こちらはあくまで一例です。個々の製品によって消費電力と起動電力は変ってきますが、平均的にはこのようになっています。例を見ると分かるとおり、中でもモーターやポンプを使用する機器は起動時に消費電力の1.2倍~5倍ほどの起動電力を必要とします。そのため、このような機器を使用したい場合には、この起動電力を十分にカバーできる出力を持った発電機を選ばなくてはなりません。
例えばノートパソコン(消費電力200W/起動電力200W)と、ハロゲンライト(消費電力250W/起動電力500W)、電動ドリル(消費電力300W/起動電力600W)を同時に使用したい場合は、消費電力ではなく起動電力の合計、200W+500W+600W=1300Wよりも大きな出力を持つ発電機が必要ということです。
ちなみに、発電機のカタログなどを見ると出力電流の表記にはWではなく、VAという単位が用いられています。ちょっと分かりにくいのですが、W(ワット)とVA(ブイエイ)はどちらも1秒間に消費される電気の量を表した単位。
使用機器で消費される電力がWで、発電機から出力される電力がVAです。特別な換算は必要ありません。1Wは1VAです。そして、1000Wは1kVAです。ですので1300Wは1.3 kVAとなります。簡単ですね。
◆ サイズ、重さ
発電機は、小型のものでも想像以上にかさ張り、また重量もかなり重いものです。より出力の高いものほど基本的には大きく重たくなると考えてください。たとえコンパクトな設計のものでも、本体重量は20kg~と女性が一人で運ぶには結構な負担になります。
大きさや重さがあまりに大きな負担になる場合、アウトドアレジャーや防災用としては使いにくいこともあります。販売店の売り場や、メーカーのカタログやWEBサイトなどでサイズと重量は必ず確認しておきましょう。また持ち運ぶ際は発電機だけでなく燃料となるガソリンやそれを入れる携行缶、カセットガスボンベなども必要です。そのスペースや重量も頭に入れておく必要があります。
このように発電機を選ぶ際は、出力やタイプだけでなく、利用の目的や使い方、自分や家族が持ち運ぶことができるのかなども考慮したうえで選ぶようにしましょう。また、発電機に合わせてそれを運ぶためのキャリーなども一緒に揃えておくことをオススメします。
◆ 騒音
発電機はエンジンを使用しているので、発電中はどうしても騒音が発生してしまいます。基本的に出力が大きいものほど騒音も大きくなります。アウトドアレジャーなどでは周囲もうるさいのであまり気にならないかもしれませんが、住宅街などでは気をつけないと近隣の方に迷惑をかけてしまうこともあります。そのため音も選ぶ際の大きなチェックポイントになるでしょう。
また、音量だけでなく発電機は連続して使用することが前提ですので、耳障りな音が途切れることなく発生してしまいます。人によっては連続するその音がストレスに感じることもあります。発電機を使用する際は周囲からできるだけ離れた場所に配置するような心遣いも必要でしょう。
全てではありませんがメーカーのカタログやWEBサイトでは、発生する騒音のレベルが記載されている場合があります。気になる場合はそちらを参考にしてください。

4章:発電機によって使える燃料が違う

発電機は燃料を燃やし、発電体をエンジンで回転させることで発電しています。使用する燃料は主にガソリンとカセットボンベですが、より一般的なのはガソリンです。ガソリンは入手も容易ですし、長時間安定してエンジンを動かし続けることができるので、得られる電力も安定しています。
ただし、ガソリンは扱いに注意が必要です。常温で液体の上、揮発性がとても高いので持ち運ぶだけでも慎重さが求められます。キャンプ用に少しだけ持って行きたいという場合でも、灯油用のポリタンクなどに入れるのは絶対に避けなくてはいけません。必ずガソリン専用の携行缶に入れる必要があります。保管に関しても注意が必要です。
一方、家庭用の小型発電機の燃料として徐々に増えてきているのがカセットガスボンベです。カセットコンロなどに使われているあのカセットガスを発電機の燃料として使用するというものです。カセットガスなら燃料もホームセンターやスーパー、ドラッグストアなどでも簡単に入手できますし、缶入りですので保管も簡単です。またカセットコンロと燃料を共用できるのも便利です。
キャンプなどに持って行くにも、夏場の車内に置きっぱなしにするようなことさえしなければ、ガソリンほど慎重さは求められません。さらにガソリンと比べると使用期限も長いため、防災用にストックしておくにもぴったりです。
ただしコストで考えるとガソリンよりも高くついてしまいます。カセットガス1本でおよそ1時間強稼動できますが、ガソリン発電機なら、タンクの容量によりますが、ほとんどの場合それより長い時間の発電が可能です。また、カセットガスは気温が5℃以下になるとガスが気化しにくくなり、エンジンがうまく始動できなくなってしまうこともあります。寒い冬場のアウトドアでは、十分に能力を発揮できない可能性があるのです。
本格的に使いたいならガソリン、アウトドアレジャーなどで短時間手軽に発電したいという場合はカセットガスといった使い方が向いていると言えるでしょう。
また、いざというときのための防災用としては、燃料が備蓄しやすくコンパクトなカセットガス式が向いているかもしれません。
◆ 発電機の使い方(ガソリン)

(1)
周波数切替スイッチで、東日本は50Hz、西日本は60Hzに設定する。
(2)
カバーを外し、エンジンオイルを確認。少ないときはオイルを補給する。
(3)
発電機にガソリンを補給する。
(4)
燃料キャップつまみをONにする。
(5)
次にエンジンスイッチを運転に合わせる。
(6)
チョークレバーを始動位置に合わせる。暖機が済んでいる場合は不要。
(7)
始動用のグリップを静かに引き、一旦重くなる場所で止めたら、勢い良く引っ張る。
(8)
エンジンが安定したら、チョークレバーを戻す。
(9)
使用機器のスイッチは切っておき、コンセントへプラグを差し込む。
(10)
電気機器のスイッチを入れ、使用する。
◆ 発電機の使い方(カセットガス)
(1)
周波数切替スイッチで、東日本は50Hz、西日本は60Hzに設定する。
(2)
カバーを外し、エンジンオイルを確認。少ないときはオイルを補給する。
(3)
発電機のボンベカバーを開け、操作レバーが解除の位置にあることを確認してから、ボンベの赤いラインを下側にして設置する。操作レバーを固定してからカバーを閉じる。
(4)
次にエンジンスイッチを運転に合わせる。
(5)
始動用のグリップを静かに引き、一旦重くなる場所で止めたら、勢い良く引っ張る。
(6)
使用機器のスイッチは切っておき、コンセントへプラグを差し込む。
(7)
電気機器のスイッチを入れ、使用する。
このようにカセットガスタイプのほうが手順は簡単になります。基本はどのメーカーのものでもほぼ同じです。
ちなみにアウトドアレジャー用の発電機としては、本格的な使用には耐えませんが、とてもユニークなものがあります。それは木や小枝などを使用するキャンプ用のストーブです。燃やした際の熱を電気に変換し内蔵の充電池に充電できるという、いわばコンパクトな火力発電機です。
小枝などを集めてストーブの中で焚き火をすると、調理ができる上に電気まで作ってくれるというものです。本体にUSBポートが付いているので、焚き火をしながらスマホなどの小型の電気機器を充電することが可能です。出力はわずかですが、いざというときに役に立ってくれるかもしれません。ボトルサイズの小型ストーブなので防災用品の一つとして備蓄しておいても良いかもしれません。
このように発電機は燃料によって、機能や使い方に違いがあります。こういったことも考慮した上で、使用目的に合った発電機を見つけるようにしましょう。
5章:発電機が活躍するシーンとは

照明、エアコン、テレビ、通信、電車などもそうです。現代の私たちの生活インフラは、基本的に電気によって支えられています。もし短期間でも電気の供給が絶たれてしまえば、都市部などでは大混乱に陥ってしまうでしょう。
普段は特に意識せずとも当たり前のように手に入る電気ですが、あくまでそれは電源が供給されている環境にいてこそ。例えばアウトドアでは自宅のように簡単に電気を手に入れることはできません。そんなときに活躍してくれるのが発電機なのです。
どんなシーンに役立つでしょうか。例えばキャンプやバーベキューなどのアウトドアレジャーでも便利でしょう。町内のイベントでの屋台などでも活躍してくれるはずです。またDIYで愛用の電動工具を使う際の電源として、利用の幅を広げてくれるでしょう。それに万が一の防災用としても一つあれば、いざというときに役立ってくれるはずです。
このように発電機が活躍するシチュエーションはさまざまに考えられますが、具体的には利用シーン別でどのように役立つのでしょうか。それぞれのシーンごとに向いている発電機のタイプなどと合わせて紹介します。
◆ キャンプやアウトドアレジャー
アウトドアへ持ち出すことが前提のキャンプや釣り、バーベキューなどのレジャーでは、持ち運びがしやすい小型のインバータータイプの発電機がオススメです。ホットプレートやコーヒーメーカーなどの調理器具、夜間の照明やスマートフォンの充電などまで幅広く活用してくれるでしょう。
◆ DIY
DIYで電動工具を使用されているなら、従来型の発電機がオススメです。注意点は起動電力。電動丸ノコや電動ドリルなどの電動工具はモーターを使用しているものがほとんど。使いたい工具の起動電力の合計値を計算して、十分な出力を持ったものを選ぶようにしてください。うまく活用することで、作業の効率を大幅にアップさせることができます。自宅やガレージから離れた作業場でも愛用の電動工具が使えるということは、大きな魅了でしょう。
◆ 野外イベント
夏祭りや運動会などのイベント、野外ライブなどでも発電機は役立つはずです。調理機器の電源、露天などの照明などとしてだけでなく、音響機器の電源としても良質な電気が供給できるインバータータイプの発電機なら大活躍してくれるでしょう。ただし音響機器は消費電力が大きくなりますので、十分な発電能力を持ったインバータータイプが向いています。
◆ 防災用
以前の震災のときにも発電機は避難所で活躍しました。自然災害はまたいつ起きるかわかりません。地震だけでなく台風や豪雨、大雪などの際にはいきなり停電が起きることもありえます。そんな時に一台災害時用の発電機を用意しておくと安心です。照明や暖房器具、扇風機、調理器具などの電源を確保できれば避難時にもストレスが軽減できます。発電機を災害時用の備蓄の一環として考えると、カセットガスタイプのインバーター発電機がオススメです。カセットガスは保管期限が長く、また簡単に手に入れることができるからです。
まとめ
アウトドアレジャーからDIY、そして防災まで、発電機はさまざまなシーンで電気を使った機器の使用をサポートしてくれる、非常に便利なものです。エンジンを搭載しているということで、扱いにくさを感じる方もいるかもしれませんが、ガソリンエンジンタイプだけでなく、カセットガスを使える手軽なものも今は増えています。そういったタイプならその使い勝手はカセットコンロとほとんど変りません。誰にでも簡単に使えます。
発電機は一台持っていれば、キャンプやバーベキューの楽しみ方を広げてくれますし、またいざというときの電源としても役立ってくれるはず。ご紹介したポイントを参考に、是非購入を検討してみてはいかがでしょうか。