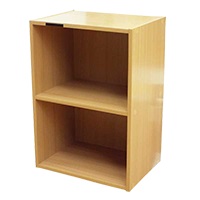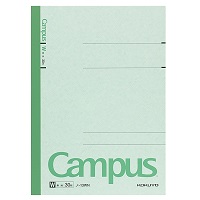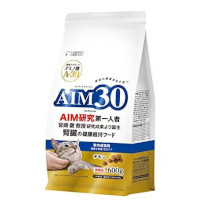目次
1章:主なのり・接着剤の種類
2章:接着剤やのりの選び方
3章:接着剤・のりの塗り方のコツ
まとめ
のり(糊)や接着剤は素材同士を接合するために使われる道具です。用途や形状などが違う商品がさまざまあり、特徴も多種多様です。ここではのりと接着剤の違いや、のりの選び方、塗り方のコツなどをご紹介します。
1章:主なのり・接着剤の種類
それぞれの違いを覚えましょう
まずはのりと接着剤の使い道と、種類についてご説明します。
【 のりや接着剤の代わりは昔からあった 】
のりと接着剤の違いですが、どちらも物を接着する際に使います。のりは紙などを貼りつけるときに、接着剤はプラスチックや金属などを接続するときに使うなど、用途を分けている人もいます。
のりと接着剤の原点ともいえるのが、今から約1万2000年前の天然アスファルトです。天然アスファルトとは、石油の油分などが蒸発した後の残留物が化学反応を起こしたものです。昔はこれを使い、石と棒をくっつけて槍にしたり、貝殻などを接合してアクセサリーを作ったり、大掛かりな建造物を造ったりしていました。
それからしばらくして、ニカワと呼ばれる接着剤が誕生します。これは、動物の皮、骨、内臓などを煮て冷却・乾燥させたものです。中国、エジプトなどで使われた後、7世紀以降になってようやく日本でも普及し始めました。今でもニカワは和紙の加工や染料を日本画に定着させるときなどに使われています。
日本では昔、物と物をくっつけるために漆(うるし)を使っていた時期があります。漆はウルシと呼ばれる樹木から採取した樹脂を加工したものですが、金箔などを塗布するときは特に重宝されました。今でも漆は器などを装飾するときに使われています。腐敗防止や抗菌作用を付与する効果もあり、器の状態を美しく保つ上で欠かせません。
【 のりと接着剤の種類について 】
ここでは、のりと接着剤のそれぞれにおいて、販売されている商品の種類についてご紹介します。
《 接着剤 》

- ・ 瞬間接着剤
- 物同士を比較的短時間で接合できる接着剤です。プラスチック、ゴム、金属類などを接着するときに使われます。瞼や手、鼻などの皮膚にも良くつくため、使用時は注意が必要です。
瞬間接着剤は粘度が低く浸透力のあるものが一般的ですが、糸引きやタレが起こらないゼリー状タイプ、金属や木工専用タイプ、衝撃に強い耐衝撃タイプ、くっつきにくい素材同士でも接合できる高機能瞬間タイプなどがあります。 - ・ 多用途接着剤
- 接合する素材を選ばずに使える万能タイプの接着剤です。1本で色々な用途に使える上、屋外・屋内など使用シーンも選びません。マニキュア感覚で使えるタイプ、多孔質材料に適したタイプなどがあります。
《 のり 》

- ・ 液体のり
- 液状ののり全般を指します。封筒や画用紙など紙類の他、布やセロハン同士を接着するときにも重宝します。先端を紙に押しつけたときのみのりが出るタイプや、先端に特殊なスポンジがあり、のりが一気に溢れないタイプなどがあります。液体のりはオフィスやDIY、裁縫などで使われ、使い切ったら補充することも可能です。
- ・ テープのり
- プラスチックケースにテープ状ののりが入っているタイプになります。紙などにケース先端を押し当てて引くことで、接着面を作れます。片手で利用できること、のりの幅を一定に保てることなどがメリットとして挙げられます。接着面をまっすぐ引けるため、余計な箇所にのりがつきません。サイズがコンパクトなので持ち運びにも便利です。
- ・ 固形スティックのり
- のりが固形になっているものを指します。先端が平らなので、凹凸のない場所を塗る場合はきれいに仕上げられます。塗った箇所に色がつくタイプならばどこまで作業を進めたか目視で分かるため、塗りムラができません。
- ・ スプレーのり
- のりがスプレー状になったタイプです。スプレーするだけなので、スピーディかつ広範囲に作業を進めたいときにオススメです。表面に凹凸があってものりが細かく入り込みます。1本が50ml程度のタイプなら軽く、容易に扱えます。
- ・ でんぷんのり
- コーンスターチやタピオカなどを原料としたのりです。水溶性で、オフィス作業やDIYなどに使われます。でんぷんのりは塗った後に水分が染み込むことで、紙などにシワができることがあります。
- ・ ペンタイプのり
- ペン状の形をしたのりです。細いため、細かい部分に塗る作業に向いています。塗った箇所に色がつくタイプもあります。
- ・ 障子用のり
- 障子の桟に障子紙を貼りつけるときに使います。染み出たアクを止める効果のあるタイプや、カビ止め剤を配合しているタイプもあります。
《 その他の接着アイテム 》

接着剤やのり以外にも、物質同士をくっつける道具はさまざまあります。具体的には、以下のようなものが挙げられます。
- ・ 布テープ
- 段ボールや紙袋によく使われます。耐水性があって粘着力が強く、道具を使わなくても手で簡単にカットできます。梱包用に適した薄手タイプ、テープの上に油性ペンで文字を書けるタイプなど種類はさまざまあり、カラーバリエーションも豊富です。身近な用途で使われることが多いため、子供から大人まで幅広く認知されています。
- ・ 養生テープ
- 引っ越しや内装工事のときに、建築物に物がぶつかっても傷がつかないように保護したり、素材を仮固定したりするときに使われるテープのことです。粘着力は強めですが、剥がした後にのりの跡がほとんど残りません。耐水性や耐久性がある他、気候の変化に強いという特徴があります。手でちぎりやすいため、カットする道具がなくても簡単に扱えるのがメリットです。壁や床だけでなく、コンクリートやアスファルトに使えるタイプもあります。
- ・ ビニールテープ
- ケーブルの絶縁体として、電気工事や電気機器の配線、結束、固定などに使われています。粘着性、柔軟性ともに高く、気候の変化や外からの熱に強い側面があります。水道管の補修工事の場合は、水やサビつきに強いタイプを選びましょう。高温配管や工場などに適したタイプもあります。
- ・ クラフトテープ
- クラフト材によって作られたテープです。段ボールの密封や小包などの梱包に使われます。茶色の他、白などの色がついたタイプもあります。上から文字が書けるタイプや、重ね貼りができるタイプもあり、用途によってさまざまな使い分けが可能です。特殊な樹脂加工がされたものならば、防湿性、耐熱性が期待できます。
- ・ 両面テープ
- 両面に粘着性のあるテープです。壁に写真やポスターなどを貼りつけたり、紙と紙をくっつけたりすることができます。両面テープは自動車製造の各ラインで使われているタイプや、のりが残りにくいタイプ、屋外や凹凸がある場所に適したタイプ、耐熱性・難燃性に優れたタイプなどがあります。
2章:接着剤やのりの選び方
貼る対象の材質や商品の粘着力に注目しましょう
身近な文房具であるのりですが、選ぶ場合は以下の点に注意しましょう。
《 貼りつける材質に気をつける 》

のりや接着剤の用途は、紙や壁紙の貼りつけ、DIY(木工)、ラベルの接着などさまざまです。また、紙・木工用などの専用タイプもあるので、一つ一つの商品を見比べて最適なものを選ぶことが大切です。時間を短縮しつつ壁紙を貼り変えたいときは、裏面に粘着力(接着力)を付与した生のりつき壁紙を使うことをオススメします。
ところで、貼りつけにあたって専用ののりが販売されている障子紙ですが、こちらものり同様、色々な種類があります。具体的な種類を説明すると、以下のようになります。
- ・ パルプ障子紙
- パルプを配合した障子紙になります。他の障子紙よりも価格が安いため、予算を抑えたいときにオススメです。
- ・ レーヨン入りパルプ障子紙
- レーヨンを配合した障子紙になります。破れにくく、耐久性があるので、何度も貼り替える必要がありません。レーヨンが40パーセント以上配合されているタイプだと、より美しい光沢が感じられます。
- ・ 手漉き(てすき)障子紙
- 職人が一枚一枚手作業で作った障子紙のことです。比較的高価ですが、風合いが良く、機械で作られたものとは違った魅力があります。
- ・ 混抄(こんしょう)障子紙
- パルプにこうぞやビニロンなどの繊維を配合した障子紙のことです。強度が高く、独特な風合いがあるため障子にインテリアとしての役割を付与したい場合はオススメです。
- ・ プラスチック障子紙
- 障子紙にプラスチックをプラスしたものです。強度が高いため破れにくく、雨風にも良く耐えます。断熱性が優れているタイプなら、防災効果が期待できます。
- ・ 布
- 厳密にいうと障子紙ではありませんが、最近では和・洋それぞれの良さを取り入れるために障子に布が使われるようになりました。一枚布を障子にそのまま貼りつけたり、何枚もの布を繋ぎ合わせたりして使われます。
《 のりの粘着力にも注目 》
のりや接着剤がどの用途に適しているか分からない場合は、粘着力に注目してみましょう。
- ・ 強粘着タイプ
- 貼った後の剥がれにくさを第一に考えたい場合にオススメです。デメリットは一度貼りつけると剥がしにくく、貼りつける対象の材質を傷つけてしまう恐れがあることです。
- ・ 弱粘着タイプ
- 紙などを簡単にくっつけたいときに向いています。粘着力が弱いため、しっかり貼りつけを行いたい場合は強粘着タイプを選ぶことをオススメします。
- ・ 再貼りつけタイプ
- 貼ったり、剥がしたりを繰り返し行いたい(再剥離)ときに向いています。特殊タイプの接着剤ならば、接着機能の他に超耐熱を付与していることがあります。重ね塗りをすることで粘着力を強化できるタイプもあるので、気になる方は探してみましょう。
3章:接着剤・のりの塗り方のコツ
気をつけるべきポイントを押さえましょう

最後に、接着剤やのりを使うときのポイントをお伝えします。
《 種類ごとの注意点 》
- ・ 接着剤
- 接着剤は皮膚につくこともあり、乾くと落ちにくくなる傾向にあります。万が一、接着剤が不本意な場所についてしまったときに剥がしたい場合は、専用の剥がし液を使うなど臨機応変な対応を心がけましょう。
- ・ 液体のり
- 紙などに液体のりを使うと、シワになりやすいというデメリットがあります。塗る量を抑え、薄く延ばせばシワを防止することができます。
- ・ テープのり
- テープのりは先端を紙などに押し当てて使いますが、貼りつけがなかなかうまくできないこともあります。スタンプタイプならノック式なので、スライドしてのりを付着させるテープのりよりも簡単です。テープ式が使いづらい場合は、このタイプを使ってみましょう。
のりと接着剤は、使用後に必ずキャップやフタを閉めるようにしてください。そのまま放置しておくと、乾燥して使えなくなってしまいます。また、家庭に小さな子供がいる場合は接着剤を手の届かないところに保管するなどの工夫が必要です。誤って使うと、指先同士がくっついてしまうなどの事故が起こるので気をつけましょう。
《 製本について 》
製本をするとき、和綴じの場合は紙を1枚ずつ折り揃え、紙縒を使って下綴じをします。対して平綴じは針金を使って製本を行います。糸や針金を使う方法以外には、本の背をのりで固める無線綴じが挙げられます。
製本は一般の人が行うよりも業者に頼んだ方がきれいに仕上がります。見栄えにこだわりたいならば適切な業者を探してみましょう。
《 封筒について 》
封筒にのりを塗るときは、はみ出さないように気をつけましょう。もし、はみ出してしまった場合はすぐに拭き取ってください。色がついているタイプならば、どこにのりが付着しているか一目で分かるのでオススメです。ムラなく塗るのも簡単なので、気になる方はチェックしてみましょう。
まとめ
子供から大人まで、幅広い年齢層に使われているのりと接着剤。用途に合わせて商品を選んだり、使い方を正しくマスターしたりすることで、作業がスムーズに進みます。塗りムラやはみ出しに注意しながら、丁寧に使いましょう。