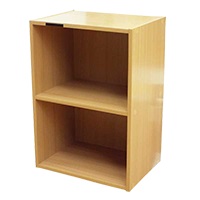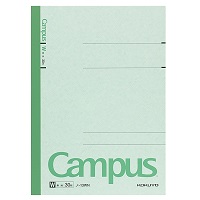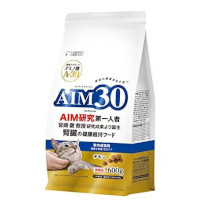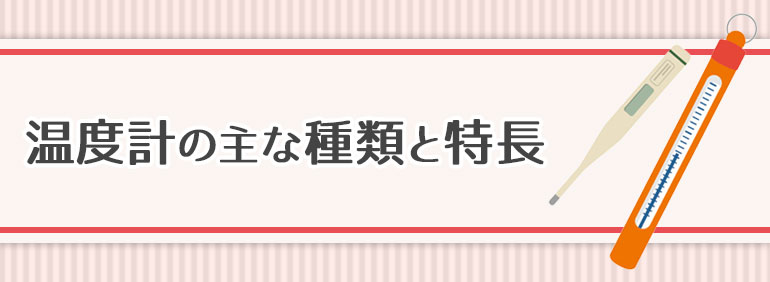目次
1章:温度計は接触式と非接触式に分かれる
2章:一般的な接触式温度計と特長
3章:非接触温度計の種類
4章:温度計の選び方
まとめ
温度計は体温や気温、水温を測るときに使われます。さまざまな種類がありますが、それぞれで構造が異なっています。今回は各温度計の特長や選び方についてご紹介しますので、今後購入する際の参考にしてください。
1章:温度計は接触式と非接触式に分かれる
接触式と非接触式の違いとは?

皆さんは、温度計がいつ発明されたかご存知ですか? 初めて温度計が生まれたのは1609年で、イタリアのサントリオによって考案されました。このとき発明された温度計は、気体の膨張圧を利用したものです。その後、1866年にドイツのC・エールレによって水銀を使った体温計が発明されると、さらに体温が測りやすくなりました。それから改良が重ねられ、1984年には日本で初めて家庭用・電子体温計が発売されたのです。
このように、体温計は今までの歴史の中で構造を変えてきました。今ではたくさんの温度計が市場にあふれていますが、大きく分けると「接触式」と「非接触式」の2つに分類できます。それぞれの特長について次の項目から説明しますので、これを機に温度計への見聞を深めましょう。
2章:一般的な接触式温度計と特長
感温部を接触することで温度を測れます
接触式温度計は、対象物に直接感温部を接触させることで温度を測る器具のことです。構造がシンプルで、価格が手頃なことで知られています。膨張式(圧力式)、電気式などのタイプが存在しますが、市場に出回っている商品を分類すると以下のようになります。
- ・バイメタル温度計
- 熱膨張率の異なる二つの金属板を使って、温度を測定しています。構造は比較的単純で、ガラス温度計よりも頑丈です。用途は幅広く、石油工業、冷暖房ダクト、工場の製造ラインなどさまざまな場所で活躍しています。サーモウェル(保護管)と組み合わせることのできるタイプなら、バイメタル温度計の温度センサーを保護できます。この他、マグネットつきのタイプ、アスファルトに差し込んで温度を測るタイプなどもあります。
- ・水銀温度計
- 内部に水銀を含み、その膨張で熱を測るタイプになります。水銀は他の液体に比べて比較的熱伝導率が良く、熱に対する反応が良いために利用されるようになりました。この水銀温度計が開発された当初、熱を測る器具がまだまだ発展途上にあったため、重宝されていました。今でも体温や水温を測るときに使われています。
- ・アルコール温度計
- 感温液にアルコールを使った温度計です。しかし、実際はアルコールだけでなく石油系の液体が使われていることがあります。このタイプの温度計は低い温度の測定に適しており、その精度は水銀温度計よりも良いとされ、その用途は多岐に渡ります。
- ・圧力式温度計
- 温度によって内部に封入されている液体、あるいは気体の圧力が変化するのを利用した温度計になります。動かすときは電源を必要とせず、耐久性もあります。感温部には水銀、エチルアルコール、ヘリウムなどが利用されます。対応できる温度幅は狭いものの、感度が良いことで知られています。
- ・熱電温度計
- 2つの金属を接触させると、その温度が異なっている場合は電流が流れます(熱起電力)。この原理を応用したのが熱電温度計です。精度が良く、工業用に適しています。
- ・電気抵抗温度計
- 電気抵抗を利用した温度計になります。これは、サーミスタと呼ばれる電子部品を利用したタイプと、白銀による電気抵抗を利用した白金測温抵抗体を使ったタイプがあります。
3章:非接触温度計の種類
放射温度計とサーモグラフィの2つがあります
非接触温度計とは、感温部を対象物に接触させずに温度測定ができる器具のことです。衛生面に配慮できるため、食品業界で使われることもあります。非接触温度計は放射温度計とサーモグラフィが良く知られていますが、その違いについてまとめてみました。
- ・放射温度計

- 物体から発せられる赤外線を利用して、温度を測る器具になります。この温度計は耐久性が高く、高温にも対応できることで知られています。この温度計を使って正しく温度を測るためには、「放射率」の設定が欠かせません。放射率とは、理想とされる黒体の放射エネルギーと、測定する物体の放射エネルギーとの比を表したものです。放射率の設定方法については、各商品の取扱説明書などに書かれています。時には黒いスプレーやテープなどを利用して、放射率の設定をすることがあります。
放射温度計の中には、レーザーマーカー機能が存在します。物体表面のどの部分の温度を測定しているかすぐに分かる機能です。連続測定ができるタイプ、コンパクトで持ち運びしやすいタイプ、防水機能のついたタイプなどバリエーションが豊富です。消耗が少ないため経済的であること、動いている物体の表面温度を測るのに適していること、測定時間が速いことなどがこの温度計のメリットとして挙げられます。デメリットとしては、物体の表面温度のみの測定しかできないこと、反射鏡やレンズが汚れたり、曇ったりした場合は測定温度が低く評されることなどがあります。
なお、この温度計はガラス越しに温度測定をすることもできます。そのときは赤外線を十分に透過する窓ガラスを選びましょう。 - ・サーモグラフィ
- 赤外線を利用して温度を測る器具ですが、先ほどご紹介した放射温度計とは少し勝手が異なります。放射温度計の場合、単一で温度を測定するときは信ぴょう性が高いのですが、広範囲で物体等の温度計測をするときは誤差が出やすくなります。その点、サーモグラフィは温度の測定範囲が広めです。物体等の温度は画像を通して確認できますが、高温は赤色、低温は青色で表示されるのが一般的です。
サーモグラフィは工場などの産業現場だけではなく、医療現場でも使われています。人の体からも赤外線は放射されているため、全身の温度分布を測定したいときには重宝されます。感温部を接触させずに温度測定ができるため、炎症や神経損傷を患っている場合も同様に使えます。
4章:温度計の選び方
用途に応じて選びましょう

温度計は、用途に応じて選ぶことが肝心です。料理のときに使えるタイプ、高温や低温に適しているタイプなど、色々な温度計を見比べて購入を検討しましょう。今は電子温度計のように、いちいち目盛りを見なくても温度が測れるようになりました。気になる人はこちらの温度計をチェックしてみましょう。
気温を測定するタイプの温度計には、湿度や日付が表示されるタイプもあります。商品は色やデザインが豊富なので、選び方次第では部屋のインテリアにもなります。あえて針が動いて温度が表示されるアナログタイプの温度計を購入するのも面白いかもしれません。こうした温度計は、ホームセンターなどで販売されているので、気になる方は足を運んでみましょう。
まとめ
接触式、非接触式、アナログ式、デジタル式など温度計にはさまざまな種類があります。今は昔に比べて安全性が高く、寸法も手ごろで、幅広い温度に対応しているタイプが見られるようになりました。熱が出たときに体温をすぐ測れるように、家に1つは体温計を用意しておくことをオススメします。